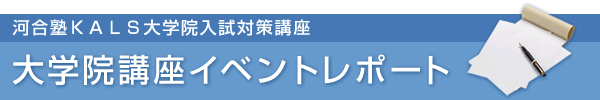国内MBA合格者座談会
一橋大学大学院経営管理研究科 合格者
早稲田大学ビジネススクール(経営管理プログラム/夜間主コース) 合格者
<2010年10月10日に新宿校で実施されたイベントの一部を収録したものです>
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
一橋大学大学院経営管理研究科 合格者
早稲田大学ビジネススクール(経営管理プログラム/夜間主コース) 合格者
<2010年10月10日に新宿校で実施されたイベントの一部を収録したものです>
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
Aさん:早稲田大学ビジネススクール(経営管理プログラム/夜間主コース) 合格
Bさん :一橋大学大学院経営管理研究科 合格者
■MBAを目指したきっかけ
――司会(KALS・田原チューター):まずは簡単に私の自己紹介をしたいと思います。昨年の春にKBS(慶應ビジネススクール)を卒業しました。その前は出版社で編集の仕事を3年ほどしていました。KALSではMBAオプション科目および講座チューターを担当しています。本日は昨年合格されたお二人にお話をお伺いしたいと思います。まず、簡単に自己紹介をお願いします。
Aさん:私は早稲田ビジネススクールで夜間のMBAのコースに通っています。昼間はプラントエンジニアリングの会社でエンジニアとして仕事をしながら、夜間のMBAに通っています。――早稲田の夜間は志望者がすごく多いのですよね。競争倍率が高くてなかなか入れないという状況なので、今日はとても貴重な話が聞けるだろうと思っています。
Bさん:私は一橋大学のMBAコースに所属しています。その前は某メーカーの営業として6年間勤務していました。――では、基本的な質問からしていきたいと思います。なぜMBAを目指そうと思ったのですか?
Bさん:私の父が企業経営者ということもあり、もともと経営に対する興味が大きかったことが第一の理由です。まずは父の会社に就職する前に、世間というものをきちんと勉強し、把握した上で就職しようと思いMBAを目指しました。――ちなみにMBAという存在を知ったのはいつ頃ですか?
Bさん:大学3、4年生のころです。テレビ等でアメリカのMBAが流行ったときです。―社会に出て5年でMBAに進もうと思ったきっかけは何ですか?
Bさん:私の父が大病を患ったというのもありますが、いずれは会社を継ぎたいという意思がありましたので、この辺できちんと勉強しようと思いました。Aさん:私がMBAを目指したきっかけは、当時勤めていた会社(プラントエンジニアリング)が韓国企業との激しい低価格争いに巻き込まれていました。このままだと当社のビジネスは先細りかな・・・という危機感がありました。それを打開するための知識やスキルを身につけることはできないかと考えたときに、新聞広告の記事を見てMBAを目指すようになりました。
――それでは、昔からMBAを目指そうと思っていたわけではなくて、ちょっとしたきっかけから目指すようになったわけですね。
一般受験の場合は、英語と専門科目の対策法を教えてください。また、研究計画書についても教えてください。
Aさん:そうですね。私はもともと工学部出身で、ずっとエンジニアの仕事をしてきましたのでMBAを知る機会はありませんでした。
――エンジニア出身者がMBAを目指す際に何かプラスになることはありますか?
Aさん:工学部でやってきた勉強とは全く接点がないので、大変な一面があると同時に新鮮な面もあります。MBAで学ぶことが自分のやりたいことだと思えれば、とても意義のあることだと思います。――早稲田の夜間のMBAで理系出身者はどのくらいの割合でいますか?
Aさん:早稲田の夜間にはMBAとMOTのコースがありまして、MOTのコースですと8、9割は理系出身者です。しかしMBAのコースでは1割にも満たないと思います。
また、早稲田の夜間のコースでは実務経験3年以上が求められるので、学卒は入れません。そのため社会人しかいません。
――では、理系だからといって入試が不利になるということはないですか?
Aさん:ないと思います。学校によって違うかもしれませんが、早稲田の場合は全く関係ありません。■受験校の選択
――Aさんはなぜ早稲田にしようと思ったのですか? また、早稲田しか受験されなかったそうですが、もし不合格だったらまた来年受験ですよね? 非常にリスクが高いと思うのですが。
Aさん:働きながら通える夜間を中心に探し、いろいろ調べたり説明会に行ったりしてみて、自分のやりたいことに一番フィットしたのが早稲田でした。やりたいことというのは、私の問題意識が韓国企業との競争でしたので、MBA用語で言う「競争戦略」をしっかり学ぶことでした。確かに早稲田しか受験しないというのはリスクが高く、先生にも併願を勧められました。しかし私がMBAを知ったのは去年の9月頃で、受験までにあまり日がなかったので一発勝負にかけてみようと思ったのです。
――Bさんは早稲田ビジネススクール(全日制) 、KBS、一橋の3校に合格されていますが、なぜ一橋を選んだのですか?
Bさん:一橋を選んだ理由は3つあります。1つ目は、もともと営業職時代にマーケティングをかじっていましたので、マーケティングの先生に興味がありました。2つ目は、学費の面で国立を選びました。3つ目は、面接試験を受けた際に、面接官との会話のキャッチボールがとてもしっくりきて、一番手ごたえがあったからです。■受験対策
――では次に、準備期間、勉強方法、対策について教えてください。
Bさん:私は情報収集と勉強を含めて、だいたい半年くらいの準備期間です。いろいろ手を伸ばして勉強したことはありません。与えられたテキストで予習と復習をしました。私は8時から22時まで仕事をしていたので、予習は朝起きてからしており、土・日はKALSにこもって勉強しました。英語は大学受験で使っていた英単語集1つとKALSのテキストでの勉強でした。他は過去問を入手して解いていました。KBSの英語の問題は難しいほうだと思います。簡単な問題を間違えないで答えることが重要です。面接も大きなウエイトを占めているので、面接対策はしっかり行いました。3対1の圧迫面接で「なぜ学びたいのか」「なぜKBSなのか」など細かく本質を突いた質問をたくさんされます。何度も「なぜ」という言葉を自分の中で繰り返しながら、突き詰めて考える練習をしました。ただ、研究計画書に沿って質問をされるので突拍子もない質問はされません。
Aさん:私は準備期間があまりなかったので早稲田に絞り、『MBA論述対策』を受講しました。すでにLIVE講義は終了していたのでDVDで勉強しました。平日の夜と土日のどちらか一日は自習室にこもって、DVD補講をしたり、自分で過去問を書いて論述対策をしたり、講義終了後には小川先生に添削をしていただきました。
早稲田の夜間の問題はある程度の社会的な知識が必要になります。ベースとしての予備知識がないと論点を設定するところでつまずくからです。また、ときどき社会福祉・年金・医療保険の問題が出されますが、これらはMBAの受験対策で学ぶところではないので普段から日経新聞を読んで知識を増やしました。
準備期間があまりない方へのアドバイスとしては、規定時間内に規定文字数をきちんと書く訓練をし、その中できちんと論点を設定できるようにすること。社会常識として、日経新聞、日経ビジネスには目を通しておくことだと思います。
早稲田の夜間は願書を出す時点で、どの先生のゼミに入るかを設定します。面接は自分が希望する先生と、そのほか2人の先生と私で行われました。圧迫面接ではなく、なぜここで勉強したいのか、これからどうしたいのか、それから仕事に関する質問をされました。Bさんと同じで、「なぜ」ということをよく考えておかないと答えられないものでした。KALSでは面接の相談にも乗っていただいたり、志望理由書の添削をしたりしてもらいました。それを通じて準備ができたのでとても助かりました。
――では、研究計画書を書くポイントは?
Aさん:自分の持っている問題意識をいかに他の人にわかりやすく、伝わりやすく書くかということです。Bさん:一貫性を持って書くことです。
■受験対策
――Aさんは仕事と勉強を両立していますが、どうですか? きつくないですか?
Aさん:大変だろうと思ってはいましたが、実際、相当に大変です。まず時間が足りません。平日の夜に週3回学校に通っており、授業は7時から10時まであります。職場が横浜なので仕事を5時半には切り上げなければならないのですが、まず仕事を5時半に終わらせるのが大変です。また、授業を受けるだけでなく課題が出るので、その課題はいつやるのか、指定図書はいつ読むのかがものすごくシビアになってきます。――仕事への影響はありますか? 職場の理解はありますか?
Aさん:職場には話してあり、理解を得た上で通ってはいますが、それでもやはり大変です。出張にいけなかったり、夜遅くまでかかってしまう仕事だと断らなければならなかったり。なかには会社には言えないという人もいますが、そういう人は声もかけられないくらい大変そうです。―― 一方、気楽な学生生活を送っているBさんのお話を聞きたいと思います(笑)。一橋の学生生活はどうですか?
Bさん:大変申し上げにくい部分もあるんですけど(笑)。やはり私は勉強だけやっておりますので、非常に恵まれていると思います。課題についてですが、課題はどこまでいっても100%のものはできません。自分がどこまで満足してやるかということになってくるので、本当に夜遅くまでかかるときもあるし、予習に12時間かかることもあります。毎日ではないですがピークのときでは睡眠時間が2、3時間になったりします。そういった面を含めて、自分の中できちんと計画をたてて勉強するということは、自分の将来に対する良い練習だと思っています。■MBAの価値
――お二人にとってMBAの価値というのは、どういうところにあると思いますか?
Bさん:多くの財務指標であったり、ケーススタディの数をこなしていくことで知識が増えます。知識が増えると色々な視点からものごとを考えられるようになるのですが、これはすごく重要であり、価値のあるものだと思います。Aさん:職場を離れてさまざまな業種の方と一緒に学んでいると、幅広いバックグラウンドを持った方々と利害関係なく自由な議論ができます。そこから新しい刺激を得られるという点は、在学中に感じる1つの価値だと思います。将来を考えた上での価値としては、ハードな生活を通してこれまでの自分のキャリアを客観的に見直し、自分は将来どうしたいんだろう、何をやりたいんだろうと考え直し、目標に向かって頑張る覚悟、決意が形作られることだと思います。
――では最後にこれからMBAを目指す方たちへのアドバイスをお願いします。
Bさん:まだまだアドバイスができる立場ではないですが、将来、今ここにいらっしゃる皆様と何らかの形で一緒にお仕事ができたらいいなと思っています。Aさん:私も偉そうなことは言えませんが、受験期間は皆さんすごく不安だと思います。私もそうでした。本当に合格できるのか、合格してもついていけるのか、など色々と悩んで暗くなりがちだと思いますが、それを乗り越えて通うだけの価値はビジネススクールにはあります! ぜひ頑張ってください。