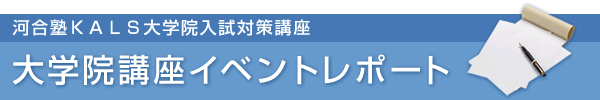慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 合格者
一橋大学大学院 商学研究科 経営学修士コース 合格者
<2011年5月22日に新宿校で実施した「合格者講演会」の模様を一部採録したものです。>
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
合格者Aさん:慶應義塾大学大学院 経営管理研究科
合格者Bさん:一橋大学大学院 商学研究科 経営学修士コース
合格者Cさん:一橋大学大学院 商学研究科 経営学修士コース
(司会:河合塾KALS・田原先生)
田原先生:本日は3名の合格者の方に来ていただきました。まずは自己紹介からお願いします。
Aさん(女性) :私は今年の春から慶應義塾大学大学院経営管理研究科(KBS)で勉強しています。大学卒業後は5年間某通信会社に勤めておりました。MBAを目指す理由というのは、いずれ私も父の事業を継いで経営者になりたいという思いが昔からありましたので、2009年の冬頃にキャリアチェンジを考え始め、色々ある選択肢の中でMBAが一番自分に向いていると思い、2010年の春からKALSに通い出しました。
Bさん(男性) :私は明治大学を卒業し、新卒で一橋大学大学院商学研究科経営学修士コースに入学しました。父親が事業を営んでいることと、自分自身で起業したいという思いもありましたので、MBAを目指すことにしました。
Cさん(男性) :私は慶應大学を卒業後、新卒で一橋大学大学院商学研究科経営学修士コースに入学しました。
大学では金融について勉強してきましたが、マクロ的なことでしたので、大学院ではミクロ的な実務に関することを学びたいと思いました。
田原先生:Aさんは自分に向いているのがMBAだと思ったのはなぜですか?
Aさん:中小企業診断士、会計士など独学でコツコツ勉強するよりも、授業に参加しながら勉強していくほうが向いていると思ったからです。
田原先生:BさんとCさんは社会経験が無いなかでMBAを知ったきっかけは何ですか?
Bさん:NHKのテレビ番組からです。
Cさん:大学3年の就職活動の時期です。将来、企業の財務的な意思決定に携わる仕事がしたいと思いMBAを強く意識するようになりました。
田原先生:入学試験を突破するために、どのような対策を取りましたか?
Bさん:私の場合は、英語・小論文・面接・研究計画書のすべてを完全にKALSに頼って勉強しました。なぜならKALSの課題をきちんとこなせば、絶対に合格するという確信があったからです。
Cさん:私は大学時代、英語の勉強をさぼってしまっていたので、基礎的な勉強が必要でした。まずは単語を徹底的に覚え、大学受験時代に使った参考書で文法の復習をしました。その後はひたすら文章を読みました。小論文は一人で書いていても上達しないと思ったのでKALSに来て、論文を書いては添削してもらうことを繰り返しました。また論文のネタを増やすために経営学の用語集を勉強したりケースブックを勉強したりしてネタを身につけていきました。研究計画書の明確なテーマは大学時代からあったので、それを中心に書いていきました。
Aさん:4月からKALSに通っていましたが、6月頃は仕事のピークと重なり、とてもハードな日々を過ごしていました。9時から22時まで仕事があり、帰宅後はKALSの論文や課題を持って近所のファミレスで深夜2時まで勉強するということの繰り返しでした。7,8,9月の時期は、仕事5:勉強4:生活1という感じでした。
仕事をしながら勉強するために、KALSを選んで本当に正解でした。なぜなら、小論文に関して言うと、すごく広いテーマを一から自分で組み立てて論述することはとても難しく、実際に書いてみると、ベースになるビジネスの知識が少なすぎて、すごくつたない論文になってしまいました。しかしKALSのテキストできちんと章立てになっているものや、与えられたテーマに対して、まず教科書を読んで知識を入れ、論文を書くということをしていくうちに、ちゃんとした論文が書けるようになるからです。
社会人として新卒の方より有利だと思ったことは、会社には経理をやっている先輩方が沢山いることです。またMBAに行くぞ!ということを日々念頭に置きながら、あるプロジェクトがあったときにはどのような戦略で出来ているのか、うちの会社は事業部制なのか、どういった体制になっているのか、といった疑問を持つことによって、実際の生活の中で小論文の対策ができたことです。
田原先生:では実際の入試の難易度、英語・小論文・面接の感触などを教えてください。
Aさん:KBSの英語の試験に、数学が組み込まれた問題が出たときはびっくりしました。あとは問題量が多かったので、速読ができないと時間が本当に足りないと思います。
面接はかなり圧迫面接でした。私もそうなのですが、一橋と併願している人がほとんどなので「なぜKBSなのか、何を思ってKBSにしたのか」ということを明確にしておく必要があります。また、説得力がないと先生の厳しいツッコミには耐えられないと思います。
Bさん:私も一橋とKBSを受験しました。一橋はKBSに比べて文章は長かったのですが、今年に関して言えば、英文は比較的容易だった気がします。長めの和訳、6問くらいの正誤問題という設問の形は例年と同じでした。
一橋の面接では研究計画書の内容と成績についての2点を聞かれました。KBSでも研究計画書の内容について聞かれたのですが、明らかに圧迫面接でした。
Cさん:私も一橋とKBSを受験しました。私の場合、一橋はかなり圧迫面接で、学校の成績について聞かれたり、ゼミについて聞かれたりしました。
一方、KBSはいたって普通の面接でした。研究計画書を中心として、志望動機、将来の夢、卒業論文について聞かれ、あまり緊張もせず、すんなり終わった印象を受けました。
しかし、筆記試験においては一橋のほうが時間配分も多く、個人的には簡単な印象を受けましたが、KBSはすごく難しく、正直手ごたえはなかったです。
田原先生:みなさん研究計画書の作成には苦労したかと思いますが、作成するにあたって何かアドバイスはありますか?
Aさん:私は締め切りの朝までかけて、本当にギリギリで完成させたので、自分が何をやりたいのかを今のうちから決めておいたほうがいいでしょう。最低1ヶ月は絶対にとっておくべきです。
Cさん:良いアイディアが思いついたときはメモするようにしておくと、後々書きやすくなります。KBSの研究計画書は分量が多いうえに手書きなので、あらかじめ考えておいたほうがいいでしょう。
田原先生:KALSで学んだことがどのように入試に役立ちましたか?
Aさん:やはり論述力です。序論・本論・結論の書き方を繰り返し練習することで、初めて見る問題でも、きちんと書くことができました。
Bさん:優先順位をつけていくなら、一番は小論文です。論理的な書き方が試験で活かされました。二番目は英語です。経営系の文章を読み込んだことによって、正誤問題を解く上でも役に立ちました。
田原先生:みなさんの大学院生活を教えてください
Aさん:どこに行っても同じですが、睡眠時間が足りません。午後4時半に授業が終わったあとは8時までグループワークをします。家に帰ってきてからは深夜2時、3時まで翌日の予習をしています。また、人前で自分の意見を話すことの難しさを痛感しています。
Bさん:「すごく大変」の一言です。でも自分のやりたいことなので、楽しんで乗り切ろうと思います。
Cさん:一橋の授業方針は、考え抜くことに重きを置いています。それが一番現れているのは古典講読の授業です。とにかく、考えて、考えて、考え抜くという感じです。
田原先生:それでは最後に、これから受験する方へのアドバイスをお願いします。
Aさん:とにかく時間の有効活用ということを念頭に置き、与えられた教材をフル活用して勉強してください。勉強は辛いですが、モチベーションの高い方たちと一緒に、ディスカッションができる環境に身をおけたということが、大学院に入って一番よかったなと思います。
Bさん:KALSのメンバーを仲間と思ってください。情報共有することで大学合格に近づけます。また、KALSでの勉強を全力でやることが一番効率のいい方法だと思いますので、先生たちの言うことを信じて勉強していってください。
大学院では、本当にモチベーションの高い仲間ができるうえ、元金融庁長官・金融学会の会長など、すばらしい教授陣たちに教えてもらうことができます。ぜひこれらを目標に全力で頑張ってください。
Cさん:皆さん何かしらの目標があってMBAを目指そうと考えているはずなので、死ぬ気で勉強して、ぜひ合格を勝ち取ってください。それから、私がそうだったように、KALSの先生を徹底的に活用してください!