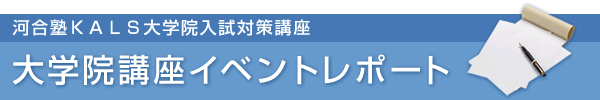●慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 合格者
●首都大学東京大学院 社会科学研究科 経営学専攻 合格者
●早稲田大学大学院 商学研究科(夜間主) 合格者
<2011年10月9日に新宿校で実施した「合格者講演会」の模様を一部採録したものです。>
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
合格者Aさん:慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 修士1年
合格者Bさん:首都大学東京大学院 社会科学研究科 経営学専攻 修士1年
合格者Cさん:早稲田大学大学院 商学研究科(夜間主) 修士1年
(司会:河合塾KALS・田原先生)
田原先生:本日は昨年度MBAの大学院を受験し、見事合格された1年生の方々をお呼びしています。
まずは簡単に私の自己紹介をさせていただきます。私は3年間出版業界で編集の仕事をした後、慶應ビジネススクール(KBS)に行きました。現在は河合塾KALSにてMBAを教えています。
では、みなさんにMBAを目指したきっかけを聞きたいと思います。
Aさん(女性) :私は元システムエンジニアの経験を活かし青年海外協力隊としてボランティアに参加していました。そこで一緒に活動していた仲間が何人か社会起業を始めたのですが、彼らは情熱ばかり強くて利益を出すということが出来ていませんでした。私は元々ビジネスに興味があったこともあり、ビジネススキルを身につけて彼らのサポートまたは自分で社会起業ができたらいいなと思ったことがMBA進学のきっかけとなりました。
現在はKBSの1年生ですが、とてもハードで睡眠時間は3時間半から多くて5時間というのが普通です。
Bさん(男性) :私はモバイルインターネット業界に所属しながら、現在は首都大学東京大学院に通っています。私は20代で起業し3年ほど会社を運営していましたが、能力の限界、オーナーとの衝突などが重なり、失敗という形に終わりました。そこで何で失敗したのか、成功している会社と失敗している会社の違いは何なのか。そういったところを明らかにしようと思いMBA進学を決意しました。
Cさん(女性) :私は国内化粧品メーカーに勤務しており、現在入社6年目になりました。実務では店頭のセールスプロモーションに従事しております。私がMBAを目指したきっかけは3つあります。
1つ目は、弊社はワンブランドで限られたチャネルしかありません。それゆえ、入社5年目で自分の視野の狭さや知識の無さに気づきました。
2つ目は、弊社のマーケティングの手法に疑問を抱いたとき、この疑問点を自分の提案で何か解決出来ないかと思いました。しかし自分には何の知識も理論もありませんでした。
3つ目は、女性のキャリアプランを考えたとき、学業に専念できるのが今の2年間だと思ったからです。現在は、早稲田大学商学研究科(夜間主)に通っています。
田原先生:「女性のキャリア」という言葉が出てきましたが、今MBAで女性がとても増えてきています。私がKBSに入学したときは女性が1割弱でしたが、今は2割くらいです。どこの大学でも言えることですが、女性の割合が増えているということは、それだけ女性にもチャンスがあるということです。女性の方も積極的にチャレンジしてください。
次に、なぜ予備校(KALS)を利用したのかを教えてください。
Cさん:私は理系出身のため、経済やお金の基礎的な知識がありませんでしたので、これでは合格できないと思い予備校に通うことにしました。もともと夜間のMBAに行こうと決めていたので、早稲田、首都大、筑波に強いといわれるKALSともう一つ別の予備校を視野に入れていました。説明会に参加した結果、KALSのほうが魅力的だったのでこちらに決めました。
Bさん:私は2つ理由があります。まず、私は怠け者なのでモチベーションの高い人たちと一緒に勉強することで、モチベーションを高めつつ勉強しなければならないんだという環境を作りたかったからです。
2つ目は海外MBAを検討していたのですが、会社を辞めてから半年くらい遊びすぎた結果、貯金がなくなり海外MBAどころではなくなってしまったので、国内MBAにしました。そこで国内MBAの合格者を多く輩出している予備校を検索したところ、KALSともう一つ引っかかりましたが、交通の便、コスト面を考慮した結果、KALSにしました。
Aさん:私は以前KBSを受験したとき筆記は通ったのですが面接で落ちた経験があります。面接で落ちたということは、自分の説明能力やアピール力の無さが原因だと思い、独学ではなくきちんと予備校に通おうと思いました。中学生のときに河合塾に通っていたこともあり、あまり他とは比較せずにKALSに決めました。
田原先生:独学ではなく予備校に通うメリットは何ですか?
Aさん:一番大きなメリットは過去問をメインに勉強できたことです。独学では慶應義塾大学(学部)の赤本で勉強しており、大学入試向けの英語対策をしてしまっていました。しかし河合塾では過去問のほかにエコノミスト、HBR(Harvard Business Review)などの英文記事を教材として勉強したおかげで、だいぶボキャブラリーが培われました。実際に私が受験したときもHBRから問題が出たとこともあり、河合塾に通うことで効果的に勉強ができました。
Cさん:(KALSの講義は)ビジネススクールの中で学ぶ経営戦略やマーケティング戦略に出てくるような基礎の部分に触れていく内容でしたので、考え方のトレーニングが出来ました。KALSで勉強し始めた当初は全く知らないことばかりで、自分の言葉では説明できないことばかりでした。「MBA論述対策」の授業の第1回目と2回目の宿題には4,5時間かけた上に、自分の頭だけでは解決できず、色々調べて書いていました。しかし最後には経営とは何かを文字で書けるようになり、半年の受講期間で入試で問われる論述のレベルまで完成度が高まりました。
Bさん:私は論述を書く上で一貫性にかけるという部分が欠点でした。先生からも何度も指摘されていました。しかし最後の最後まで先生に添削をしていただいたり、先生からの課題もすべてこなしたりすることで、自分を追い詰めてトレーニングすることができました。
田原先生:研究計画書を書く上で苦労した点は何ですか?
Aさん:一度書類は通っていましたが、自分の経験やなぜKBSを選んだのかが書けていなかったので、それらを先生と話し合いながら肉付けすることに専念しました。受験が9月でしたので7月頃から研究計画書に着手し始め1、2ヶ月かけて完成させました。私はKALSの先生を始め、職場の上司や知り合いの教授など人脈をフルに活かして研究計画書を見てもらいました。
Bさん:私は研究計画書のテーマ設定に苦労しました。11月の受験にもかかわらず6月から本を読み始めたため、7月の第1回目の研究計画書指導ではかなり叱られました。自分が興味を抱いている分野に対しての専攻研究がありますので、本や論文は必ず読まなければならないと思います。私はマイケル・ポーターとJ・バーニーの本を参考に読み、論文は国立国会図書館で引っ張ってきました。完成までには3ヶ月を要しました。
Cさん:私もテーマ設定に苦労しました。早稲田(夜間主)はモジュールを自分で決めて受験をします。私はマーケティング戦略モジュールというもので恩蔵直人先生のモジュールに決めていたので恩蔵先生の本4,5冊を参考に読みました。
田原先生:恩蔵先生はすごく競争倍率の高い先生だと思うのですが、実際面接ではどのようなことを聞かれましたか?
Cさん:面接官は恩蔵先生とマーケティング関連の先生2人の計3人でした。内容はシンプルなもので、経歴・志望動機・研究計画書の中身・本当に学校に通えるかどうか、でした。その中でも、先生の研究分野の中に自分のやりたいことが入っているかどうか、女性が夜間のコースに通うのはとてもハードだが本当に2年間やり切れるのか、という質問に対して的確に答えられたことが合格のポイントだと思います。筆記試験はKALSで勉強していれば簡単に感じるようなものでした。
田原先生:BさんとAさんの入試はどのようなものでしたか?
Bさん:筆記試験は約1時間半で、選択形式の問題が6問ほどでした。出題形式は例年と少し変わっていましたが、難易度としては余裕でした。
面接は約20分で、面接官は森本先生という方と他2人でした。なぜ首都大なのか、どのような研究テーマにしたいのかをしつこく聞かれました。また、あなたなら○○社の競争戦略をどう考えるか、ということも聞かれました。
Aさん:一橋ではKALSで使った過去問とほぼ一緒でした。過去問をやっていれば英語のレベルもさほど難しく感じません。面接では伊藤先生ともう1人の先生でした。私は将来社会起業をやりたいというお話をしたところ、興味をもっていただき、その話についての質疑応答が繰り返されました。
KBSの論述は過去問と同じでした。英語は第1問が数学の問題で、レベルは高校1年生くらいですが数学の英単語がわからないと難しいかと思います。ほかには英語での質問文に対して自分の考えを英語で答える問題が出されました。
面接は自分のビジネスプランを説明して終わりました。多少の圧迫はありましたが、きちんと準備していたおかげで適切に対応することができました。KBSの場合は圧迫面接を覚悟して挑んだほうがいいでしょう。
田原先生:現在の学生生活について教えてください。
Cさん:本当にハードな生活を送っていますが、仕事柄ボロボロの状態で仕事するわけにもいかないので、毎日4,5時間の睡眠は取るようにしています。職場の上司や後輩の理解を得て、仕事は18時前に終わらせて学校に行っています。終わらなかった仕事は家に持ち帰り、授業後にこなしたりしています。
Bさん:首都大は前期後期にわかれていて、前期は本当に大変でした。授業前には必ず事前準備が必要で、これをやらないと授業についていけません。しかしMBAの大学院に入ったことで縦と横のつながりが広がるし、何よりも楽しいです。これはMBAならではの魅力だなと感じます。
Aさん:私の場合もすごく大変で、なかには大学に寝袋を持ち込んで泊り込みで勉強している人もいます。けれどもすごく楽しいというのも事実です。