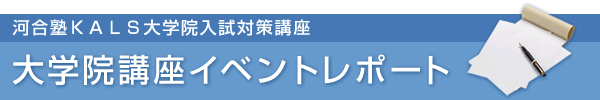KALS大学院入試対策講座 イベントレポート
河合塾KALS「大学院入試対策講座」では、大学院入試の合否を分ける情報提供のためのイベントを開催しています。ここでは、終了したイベントの中から選りすぐりのレクチャーを、まるごとお届けします!
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
河合塾KALS「大学院入試対策講座」では、大学院入試の合否を分ける情報提供のためのイベントを開催しています。ここでは、終了したイベントの中から選りすぐりのレクチャーを、まるごとお届けします!
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
心理系大学院 過去問分析〜関東地区の大学院を中心に
河合塾KALS新宿校 坂井剛 講師
皆さん、こんにちは。今日は、心理系大学院過去問分析ということで1時間弱お話をさせていただきますが、時間も限られていることから、全ての大学院について分析することはできませんし、また取り上げた大学院についても学校ごとに詳しく掘り下げていく時間はありません。詳しくは河合塾KALSの講義や、本日配布したレジュメで見ていただきたいと思います。一校一校についての詳しいお話はできませんが、大学院の過去問題をみていくときに、どのあたりに特徴が出るのかといった点に着目しながらお話しをしていきたいと思います。今回のお話では、いくつかの大学院を例にとって比較していきます。具体的には、昭和女子大学、お茶の水女子大学、明治学院大学の問題を例として挙げています。これら3大学の問題は三者三様で、違いを認識するためにはわかりやすいのではないかということで選んでみました。そして一番最後に、他の大学ということで、立教大学、立正大学、大正大学の問題も少し挙げてあります。
受験対策に過去問分析が必要なわけ
これは私が講義の中でよく言っていることで、KALSの受講生は耳にタコができるほど聞いていることですが、全般的にいって大学院入試というのは山登りと同じだと思うんですね。ベースとなる基礎的な知識というのはどの大学を受けるにしても絶対必要なものです。例えば、オペラント条件付けなどは基礎の基礎ですよね。そういった基礎的な知識の上に発展的な理論を積み重ねていくわけなんです。なのでベースとなる知識は絶対に勉強する必要があって、あとはそれからさらに上をめざしていくということです。大学院を受験するということは、頂上のそれぞれ異なる山を目指すということで、つまりふもとにあたる基礎的なベースは当然必要なんだけれども、そこから先、本当に頂上をめざすとなると、それぞれ異なるアプローチが必要だということです。1つの山の頂上をめざすとき、2つも3つも他の山の頂上をめざすことはできません。一定の知識があればどこでも受けられるというものではないんです。学校毎の対策をどれだけとれたかで合否が分かれるわけです。心理学というのはひじょうに範囲の広い学問で、学者であってもすべてを知りえない。だからこそ専門家が育つわけですが。大学院受験の対策としては、まずはベースの勉強をして、頂上アタックのラインを探る、つまり過去問題の分析をするということになります。
過去問の分析をするときに、全く心理学は初めてという方がみても、なんのことかさっぱりわからないと思いますので、今日の講演ではその部分についてある程度の話ができればいいなと思っています。いくつかの大学を参考例として取り上げていますが、過去問の見方についてはどの学校でも同じですから、今日扱わない大学を受けるとしても役に立つ部分があると思います。
昭和女子大学の場合
まず、昭和女子大学の問題を見ていきます。詳細をお話しする時間はないのですが、特徴的なこととしては、昭和女子大学の場合は、「幅広く出る」という点だと思います。とにかく幅広いです。分野の区別があまりなく、臨床心理のみの知識では合格できません。臨床心理士指定大学院をめざしているわけですから、臨床心理や発達臨床については勉強した人が多いと思いますが、それだけではダメなんですね。“心理学の基礎”が大事になってきます。形式としては、専門論文として基礎・専門の2領域。基礎領域の問1は、感覚・知覚・発達・学習・社会など心理学全般を扱う穴埋め問題が10問です。基礎領域の問2は、分野を問わず“心理学の研究”に関する論述問題で、知識のみでは対応できないような問題です。いわゆる研究法の授業で話される内容について、かなりつっこんだことを聞いてきます。
専門領域については臨床心理学に関連する問題ですが、形式や問題数、論述の問題数も年によって異なります。
それぞれについて少し詳しくみていきますと、基礎領域の問1である穴埋め問題。これは心理学の基礎知識に関する穴埋めで、例えば「感覚の閾値や主観的等価を決定するための方法を総称して( )という」のような感覚心理学の問題も出題されますが、いずれも基礎的な用語です。これができない人はそれ以上の問題には対応できないから受かりません。心理学の概論書といわれるようなものをどれだけマスターしているかにかかっています。こういった簡単な問題で失点すると致命的ですから、気を抜けない部分です。
次に、基礎領域の問2ですが、“研究”に関する設問です。研究計画の立案、信頼性や妥当性の確保など、研究に関する問題が様々な角度から問われているというものです。つまり心理学の実験ですよね。動物実験もあるでしょうし、人間の行動観察もあるでしょう。質問紙を使った調査もありますし、さらに観察もあります。実験方法は、実験、観察、調査に区分されますが、このうちのどこから出題されても不思議ではないです。特に臨床心理士をめざす方の中には、実験を苦手としている人が多いかもしれませんが、その場合は出題されたらアウトですね。逆にいうと、たまたま実験のことを知っている人が受けた場合は受かります。出来ない人が多いからです。
問題は、これに関する勉強がしづらいということなんですね。この秋受験する人は間に合わないと思いますが、来年の秋受験なら今からでも遅くありませんから、とにかく論文をきっちり読んで欲しいんですね。私は大学でも指導しているんですが、よく思うのは、論文を読むときに結構読み飛ばしている学生が多いということなんです。最初と最後だけ読んで、肝心の方法を読んでいない。専門職大学院では修士論文はないですが、そもそも関東地区に専門職大学院はないですし、大学院では修士論文を書くわけなので、絶対必要な知識です。それに修士論文を書く書かないに関わらず、そもそもこういった知識がないと、大学院に入って論文が読めないですよね。なので今はとにかく、“論文を丁寧に読む”ということを心がけてほしいと思います。研究法はそれをしないと身に付かないです。一番いいのは自分でやることですが、時間もないでしょうし、やはり論文を読むしかないでしょうね。その場合、わからないところを放っておかない。KALSの受講生なら我々講師に聞いてほしいし、大学生なら大学の先生に聞けばいいですよね。わからないところをそのままにしておくと入試で落ちます。
最後に臨床領域ですが、これは年度ごとに出題の様子が違います。例えば平成19年度2月の問題では、「次の英単語にあたる日本語の学術用語を書き、かつそれぞれの語の意味を明確にしつつその3語を関係づけて説明しなさい」という問題が3題出されています。この問題の場合は150字程度で書けばいいわけですが、150字って本当に少なくてあっという間です。せいぜいA4 3行程度です。逆にいうとこれが問題で、短いからラッキーと思う人がいたらその人がアンラッキーです。短い方が対策は立てにくいです。短い中に専門用語をもれなくきちんと埋め込んで簡潔にまとめないといけないわけですから。
臨床領域ではもう一問、この年はロジャースの来談者中心療法に関する論述問題2題が出されています。2問合わせて1000字程度でしょう。このくらいの文字数の方がむしろ書きやすいでしょうね。もちろん、何も知らないと何も書けませんが。内容はそれほど難しいものではありません。
昭和女子大学の場合をまとめると、内容に偏りがなく、ごく基本的な知識を問う問題であるということ。どれか1部分を徹底的に掘り下げるといったことはありません。また、有名な心理療法などは説明できないといけませんが、ただわかっているだけではだめで、自分で本当に書けるか、ということを確かめてみる必要があります。幅広くいろんな分野から出される以外にはクセがありません。
ところが、このあとの2校についてはかなりクセが強いんですね。
お茶の水女子大学の場合
お茶の水女子大学の場合から見ていきます。ちなみに余談ですが、昭和女子大学大学院は男性でも入学できますが、お茶の水女子大学の場合は大学院も女性のみです。お茶の水女子大学の場合は、問題形式は例年固定されています。専門試験は3部構成で、問題1は心理臨床場面の実際的な方法論などを問う論述。つまり、ケースを題材として、「こういったときにはどういうことに注意するか、どういった進め方が望ましいか」といった実際的な療法のありかたを問う問題ですから、概論書的な知識だけでは対応できず、現場の実際的問題に踏み込んだ知識が必要になってくると思われます。
問題2は実験・調査などの研究方法、統計などの実践力を問う論述ですが、これは昭和女子大学よりもっとつっこんだことを聞いてきます。研究方法にとどまらず、その先の分析に関わる統計学の知識が必要になってきます。統計学を苦手とする人は多いと思いますが、苦手といっていてはお茶の水女子大学は絶対受かりません。受けるなら統計を克服してから受けてください。
問題3は用語説明問題が10問程度。1問につきせいぜい150字程度です。
まず問題1ですが、お茶の水女子大学の臨床心理士指定コースは発達臨床コースということから、発達に関連した心理療法が問われる場面が多いです。発達障害とか、スクールカウンセラーなどに関する話ですね。例えば平成19年度では、提示された発達区分のなかから任意の2つを選択し、両者の発達上の特徴を述べた上で心理療法の特徴を比較せよという問題が出されています。これぐらいの年齢の子供だったらこういう点が問題になるだろうといった点を念頭に、考えていくわけです。任意ですからどの区分を選んでもいいのですが、違いの意識ができるかが問われます。違いを考えるときに忘れないでほしいのが、共通点も一緒に考えるということです。これはこの問題に限らず、相違点を考えるときには必ず共通点も同時に考えることが重要です。
さてケースの話も、勉強しづらい分野ですね。対応に悩んでいる人は多いのではないでしょうか。ここでもやはり論文を読めといいたい。論文には、ケース研究、つまり事例研究ですね、そういったものもあります。何らかの事例の進展について、細かに書かれているものです。これはケースのポイントとなる部分についてちゃんとまとめられているというものですが、一本読んだだけではポイントがなかなかわかりません。ケースは、何本も読んではじめて全体像が見えるというものです。遠回りのようでも結局はこれが一番近道です。応用力をつけるには、丁寧に論文を読み込んでいくのが一番です。
さらに、問題2の論述では、主に実験的研究の方法論について応用力を問う問題となっています。実験場面における実験計画とはなにか、要因配置とはなにかということです。こういった言葉を聞いてまずなんのことかわからないというレベルではお茶の水女子大学は無理です。年度にもよりますが、数字が書かれている問題が出題される場合があります。手計算が求められる問題が出されているので、カイ二乗の計算、T検定、標準偏差などの計算式は暗記していて手計算できるようにしておく必要もあるでしょう。ここまで求める大学は多くはありません。
そういうわけで、研究・統計が苦手な方は、お茶の水女子大学は絶対無理です。絶対といっても過言ではないと思います。お茶の水女子大に入ったらカッコいいでしょうけれども無理なので。はずした方がいいと思います。
問題3は用語説明問題で、発達臨床的な用語も多くありますが、扁桃体、偽相関、社会構成主義など、生理学、統計学、社会学等の用語も問われており、幅広い分野での対策が必要になってきます。
基礎ができていることはあたり前で、そこからどこまで勉強できるか、ですね。お茶の水女子大学の場合は研究者養成の色彩が強いので、こういった出題傾向になるわけなんです。実務家養成を主眼としている私立大学とは異なり、だいたい国立大学はこういった傾向が強いです。ですから研究計画書の出来というのもひじょうに大事になってくるわけです。
明治学院大学の場合
最後に、明治学院大学をみていきましょう。明治学院大学は、心理学の歴史の古い大学で、研究者養成を主眼としているわけではありませんが、問題にはかなり偏りがみられます。大問は2問で、問1は新聞記事や白書などの記事を読み、これを心理学的に考察して研究計画を考えるという問題、問2は様ご説明が10問です。問1では、例えば平成18年度春では、「校内暴力に関する統計資料とこれに関する学校教員の主観的推測(A.学校に対して好感情を持たない親の増加が理由の一因 B.近年の子供の暴力は短絡的突発的で70年代の校内暴力とは異なる) を記した新聞記事を読み、Aを心理学の知識を用いて説明 Bについてあなたの考えに基づき論じなさい」という問題が出されています。ひとつの社会現象を掘り下げていくということを、その場でやらせているわけです。大学生にこれをレポートとして課するなら、何日かかかるような問題です。
「あなたの考えに基づき」というところなんですが、これを真にうけて、ほんとうに主観的で適当なことを書くともちろん×です。“あなたの考え”とはいっても、心理学的バックグラウンドが必要で、心理学をどれだけ知っているかということが問われるわけです。他の大学の場合でもこれは同じです。
例年、題材は違っても、“資料を読んで考える”という形式は変わりません。新聞等を読む際に、覚えておいてほしいのが、識者といわれる人のコメントを真にうけず、他の考え方もあるだろう、と考えるということです。新聞って嘘が多いんですね。心理学を勉強していくと、新聞を読んでいて「このデータでこんなことはいえないだろう」と思うことがよくあります。入試でも、批判すべき話として出題してくれています。クリティカルシンキングというか、常に批判的な目で見るとうことが大事です。
さて、用語説明問題ですが、昔ながらのベタな臨床心理の問題は少ないです。むしろわりと新しい話とか、心理査定とか、とにかく臨床心理の理論だけでは対応できず、とおりいっぺんの概説書では対応できないような用語が多いです。このあたりにはその学校の先生のクセが出ているところですので、その大学の学部で、どんな先生がどんなシラバスを書いてどんな授業をしているか、を知ると、傾向が見えてくると思います。明治学院大学の用語説明問題は、心理学辞典では対応できないものが多いです。心理学辞典には最新の話は出ていないですし、すべてを網羅しているものでもありません。その学校の先生の書いている本、論文はチェックしておく必要はありますね。
立教、立正、大正大学の場合
さて最後に、他の大学ということで、あえて簡単な問題を取り上げました。立教、立正、大正大学のものですが、これらは、問題は比較的簡単で問題数も多くなく、見慣れない用語も入ってはきますが、半分以上は知っている用語ばかりだと思います。昭和女子は傾向としては近いかもしれません。簡単ということは、1問でも落とすとそれが命取りになるということです。例えば立教大学は用語が5問ありますが、1問でも落とすとその打撃がひじょうに大きいということです。論述問題は学校によって雰囲気は違いますが、立教の場合は様ご説明の延長のような論述問題で、大正大学は3問のうちから1問、好きなものを選んで解答できます。立正大学はちゃんとした論述がありますね。内容はいずれも臨床心理に偏っていますから、受験勉強はしやすいと思います。
以上、過去問題を複数並べてみてみると、学校毎の違いがみえてくると思います。秋に受験するのであれば、とにかく早く志望校を決めるということ、そして過去問題は真っ先に見て、そして対策を立てるということです。よく、過去問は最後の練習用にとっておくという愚かな人がいますが、過去問は真っ先に取り組んでください。そして、志望校以外にもいろいろ見比べて特徴を把握していくといいと思います。
以上、短い時間ではありますが、心理系大学院過去問分析ということでお話ししました。KALSでは心理系大学院過去問対策という講義も実施していますので、詳しいお話は是非講義の方にお越しください。