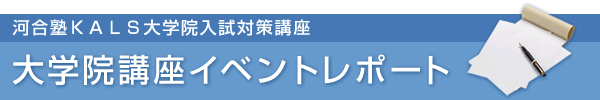臨床心理士指定大学院 合格者講演会
早稲田大学 人間科学研究科/東京大学 教育学研究科
<2010年5月16日に新宿校で実施された「臨床心理士指定大学院 合格者座談会」を採録したものです>
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
早稲田大学 人間科学研究科/東京大学 教育学研究科
<2010年5月16日に新宿校で実施された「臨床心理士指定大学院 合格者座談会」を採録したものです>
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
Aさん:早稲田大学大学院 人間科学研究科 人間科学専攻 臨床心理学研究領域 合格(修士1年)
☆臨床心理を目指したきっかけ
マスコミでの社会人生活を送る中で、社会には様々な心理的問題が多く存在していることに気づきました。もともと「人」に焦点を当てた仕事がしたいと思っていた私は、その問題を心理的、医学的、社会的な広い視点から学ぶことで、人と組織の双方に対してより良い援助ができるのではないかと思い臨床心理を目指しました。☆KALSへの入塾から学習計画まで
2008年秋にKALSに入塾し1年間の「心理系大学院受験パーフェクトコース」を受講しました。英語と専門科目はたいていの大学で課されます。社会人入試で専門科目が免除される方でも、面接時に心理学の知識を聞かれる場合がありますので、ある程度勉強しておいたほうが無難です。
私は英文科を卒業していましたので心理学のベースが全くありませんでした。そこで前半は徹底的に心理学の基礎知識を学び、後半は個別の学校対策に当てました。
☆受講科目と対策
英語対策としては読解を中心に行いました。授業では「心理系英語」「ミドルグレード英語※1」「ハイグレード英語※2」を勉強し、空いた時間はDVD補講制度を活用して勉強していました。
自主学習としては、旺文社の「基礎英語長文問題精講」の教科書を繰り返し解きました。この教科書は個人的にとてもお勧めです。「基礎」とついていますが、難易度が高くこれが完璧にできればどこの大学にも通用するだろうと思います。
早稲田大学の場合は必須となる英作文ですが、これはZ会の 「自由英作文トレーニング」を用いて勉強した他、英字新聞を毎日読み自分の考えを書く練習をしました。
専門科目対策では「心理学概論」「心理学」「小論文・論述強化※3」を受講し、基礎知識を身につけ、自分の考えを表現する力をつけました。
その他オプション科目の「臨床心理学論述演習」「心理統計学」を受講しました。
☆研究計画書について
とにかくできるだけ多くの論文を読みましょう。日常生活の中で興味のあるテーマを絞って、それに関する論文を読んでいくことをお勧めします。次に研究計画書の書き方を学ばなければなりませんが、私は研究法というものが一体どういうものなのかもわかりませんでした。まずは研究するための前提として、東大出版会の「心理学研究法入門」を読みました。また、KALSの計画書指導のガイダンスに出席したり研究計画書個別指導を受けたりして、納得いくまで先生に質問しました。
先生に質問をする際は自分の分からないところを明確にし、自分なりの考えを持って望むことが大切です。
☆研究計画書は完璧に書くべきか
内容が完璧というよりも自分が取り組もうと思った内容に対してしっかりと考え、調べ、方法論を模索したものが研究計画書に表れていればOKです。☆面接試験(早稲田の場合)
面接は20分程度です。まずは「研究計画書について」5分間のプレゼンがあります。その後面接官から質問を受けるのですが、主な質問内容は以下の通りです。
*なぜこの方法論なのか
*母集団を変えたほうがいいのではないか
*他学部出身だが、今後心理学の勉強をどう補っていくのか
*現在どのようにして勉強しているか
*大学院生活は厳しく精神的にも大変だが、覚悟はあるか
*卒業後の展望
☆大学院生活について
修士1年では、1限から授業がたくさんあり、合間には研究会が入っていたりします。土日も学校に行く日があるなどと想像以上に忙しい日々ですが、とても充実した毎日を送っています。授業はロールプレイングやディスカッション、そして実際のカウンセリング場面において必要な考え方を発表したりします。
大学院生活では横のつながりが大切になってきます。研究室の枠を超えてグループ発表がありますが、仲間と一緒に頑張っていくことで自分のモチベーションも上がります。内にこもらず、とにかく「人」と接することが大切です。
☆これから臨床心理士を目指す方へ
やる気がなくなってしまった時は、なぜ自分が臨床心理士になりたいと思ったのか、まず初心を思い出して頑張ってください。KALSにいる先生は皆、忙しくてもすごく細かいところにまできちんと対応してくれます。KALSに入ったら、ぜひ皆さん先生を追い掛け回してください(笑)※1現「英語長文読解[標準編]」※2現「英語長文読解[上級編]」※3現「論述力強化」
Bさん:東京大学大学院 教育学研究科 総合教育科学専攻 臨床心理学コース合格
☆臨床心理を目指したきっかけ
私は臨床心理士を目指すための明確な目的はありませんでした。慶応大学の法学部を卒業後、司法試験を受験するも受からず、2浪までしたときに今後の進路をどうするべきか悩みました。そのとき、心理系に興味を持ち始め、臨床心理を勉強することにしました。☆受験対策
早い段階で志望校を決めることが、受験対策で一番重要になってきます。過去問は大学院ごとに出題される問題が全然違ってきます。早くに志望校を決めて過去問を見ることができれば、無駄な労力が省けます。私の場合、東大の受験では小論文がないということを知らずに、小論文を受講し勉強していました。ぜひこのような無駄な労力は省いてください。☆勉強方法
KALSでは1年間の「心理系大学院受験パーフェクトコース」を受講しました。前期では徹底的に基礎心理を学び、後期で臨床心理を学ぶ形を取りました。
私は心理の知識が全くゼロの状態で入塾したのですが、そんな私にぴったりだったのが「心理学概論」です。この授業は基礎心理を網羅した授業ですので、自分で基礎の本を読むよりも、まとまった知識を得られます。私のような心理の知識が全くない方には大変お勧めです。
私の後期の勉強はものすごく過酷なものとなりました。勉強時間は1日10時間程度し、友達と遊ぶこともなく、抗うつ剤を飲むほどでした。授業で分からなかったところは先生のストーカーと化し質問攻めにしました。先生たちは皆さん時間をかけて受講生の質問に向き合ってくれるので、KALSに入塾した際はぜひ先生に質問しに行くことをお勧めします。
授業のほかには本を本当に沢山読み、過去問は5年分ひたすら解きました。
☆研究計画書
私は研究計画書を書くために52の論文を読みました。実際に提出したものはA4サイズ1枚程度のもので、その半分は引用文献で占められています。結構あっさりした研究計画書でしたが、面接では「法学部出身なのによく書けてますね」と言われました。研究計画書は完璧でなくても大丈夫だと思いますが、面接にもつながってくるものなので、とにかく沢山の論文を読むべきです。しかし、扱うテーマに本当に興味がないと論文を読むのが相当苦痛になります。ある程度楽しんで読める分野を選ぶべきです。また、私は「研究計画書個別指導」を計4回受けました。先生の指導は本当に的確です。☆勉強方法
☆受験生へのメッセージとにかく過去問をやりましょう。時間のない方は特に! たしかに運もありますが、基本は努力です!
入学後はかなりハードです。本当に臨床心理が好きですか? 少しでも迷いのある方は考え直しましょう!
大学院は噂に聞き及んでいた通り、本当にハードなところですが、毎日が充実していて楽しいです。皆様の合格を心から応援しています。頑張ってくださいね!