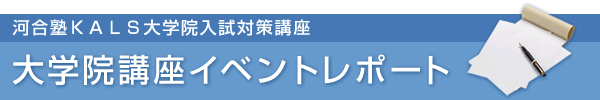税理士「税法」科目免除大学院 合格者講演会
専修大学法学研究科/明治大学グローバル・ビジネス研究科
立教大学経済学研究科/青山学院大学法学研究科
<2010年5月15日に新宿校で実施した「合格者座談会」を採録したものです>
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
専修大学法学研究科/明治大学グローバル・ビジネス研究科
立教大学経済学研究科/青山学院大学法学研究科
<2010年5月15日に新宿校で実施した「合格者座談会」を採録したものです>
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
Aさん(男性) :専修大学大学院 法学研究科法学専攻 合格
Bさん(男性) :明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 合格
Cさん(男性) :立教大学大学院 経済学研究科(社会人入試) 合格
Dさん(女性) :青山学院大学大学院 法学研究科ビジネス法務専攻(社会人入試) 合格
―まず始めに、①大学院を目指した理由、②進学を考え始めた時期、③なぜ今の大学を選んだのか・・・を教えてください
Aさん:私の実家が会社を経営していますので、将来は会社を継ぎたいと思っています。そのためには、税法や法学を勉強することが必要だと感じました。進学を考え始めた時期は、大学3年の後期からです。専修大学を選んだ理由は、教授の本を読んだときに、すごく自分に合った内容だったので、この教授しかいない!と思いました。
―他に合格校はありましたか?
Aさん:はい、高千穂大学にも合格しました。実務の学校で有名だったので併願しました。―専修大学は年間授業料を下げたと聞いていますが。
Aさん:年間80万円くらいになっています。―Bさんはいかがですか?
Bさん:私は大学3年時に簿記1級に合格しました。その際、大学の指導教授から「このまま終わるのはもったいない」と言われ、税理士試験を目指すようになりました。進学を考え始めた時期は、大学4年の4月頃でした。専修大学にも合格しましたが、やはり母校というのが大きな決め手となり、明治大学を選びました。
―明治は授業料が突出して高いですよね?
Aさん:はい、2年間で300万円ほどかかります。私が通っているグローバル・ビジネスはMBAを取得することを目的としています。学費は高いですが、夜間で通え、実務家を中心とした教授陣ということで、その価値はあります。本 当におすすめです。Cさん:私は現在、税理士事務所で働く傍ら、大学院にも通っています。働きながら税理士試験の勉強もしていましたが、仕事が大変だったことと年齢的なこともあり、大学院に行って科目免除を取ろうと思いました。進学を考え始めた時期は2009年の1月頃です。
実は、私の第一希望は専修大学の商学研究科でした。しかし私が実務をやっているということもあり、学者出身である専修大学の教授ではなく、国税局長を務められ、実務係でもあった立教大学の教授に教わったほうが自分のためになると思い、立教大学に決めました。
Dさん:大学院を目指した第一の理由は、仕事と勉強の両立が難しく、なかなか受からなかったからです。第二に、租税法をもっと深く勉強したいという思いがありました。2009年の秋に進学を考え、冬に受験しました。
青学を選んだ理由ですが、社会人が通える条件に合った学校となると、日大、青学、立教に絞られたのです。結果として青学のみ合格したのですが、ここは実務家の先生がたくさんいらっしゃるので、社会人にはお勧めだと思います。
―いつ頃から受験対策を始めましたか?
一般受験の場合は、英語と専門科目の対策法を教えてください。また、研究計画書についても教えてください。
Aさん:英語対策は大学4年の4月頃から始め、税法の勉強はその年の税理士試験が終わった後に始めました。英語は4月、5月と単語を中心に勉強し、直前期は過去問をたくさん解きました。税法は自分の言葉で答えられるよう、理解できるよう勉強しました。
研究計画書は友達と大学の図書館へ行き、本を調べるなどしてまとめました。
―英語については「法学・政治学英語」という講座がありますが、受講はしましたか?
Aさん:はい、受講しましたがとても難しかったです。―この講座はどちらかというと一橋、早稲田、慶應を目指す人や研究者の養成が含まれているので語学のほうはレベルが高くなっていますからね。Bさんはいかがですか?
Bさん:私も大学4年の4月からです。税理士試験と並行しながら勉強していました。英語対策に関して言うと、特に講座は取らずに自分で勉強していました。専門科目のみ税理士試験終了後に黒須先生の「税法」の授業を受講し、勉強していました。
研究計画書ですが、明治のグローバル・ビジネスではA4用紙で10ページほどの分量が求められます。学部時代の租税法の先生に相談をしに行ったり、KALSの合格者講演会などに参加したりするなどして税法に関する知識を揃え、何とか書き上げることができました。
―ちなみに研究計画書のテーマは何ですか?
Bさん:レバレッチドリースを使った租税回避に関する論文を書きました。船舶リース、航空機リース、映画フィルムリースを主題にして書きました。Cさん:私は4月からKALSに入塾して対策を始めました。税理士試験がありましたので、それまでは「税法」の授業に出て理解することのみに力を注ぎ、復習には重きを置いていませんでした。試験終了後、本格的に税法に関する暗記を始めました。私は社会人入試のため研究計画書と面接のみでした。そのため面接で聞かれそうなことをまとめて暗記しました。
研究計画書ですが、6月の段階で交際費課税についての論文はとりあえず書き終わっていました。しかし、当時第一志望だった専修大学の願書に所定の形式があることを知らず、7月に願書を取り寄せて初めて所定の形式があることを知りました。その中に「これまでに作成したレポートがあればその内容を書いてください」とありましたが、そのようなレポートはおろか、税理士試験が終わってから本格的に書こうと思ってほったらかしにしていた交際費課税の論文も膨らみに欠ける内容だったのです。そこで8月中旬頃に思い切ってテーマを変えて書き直しました。この時は、願書は早い段階で取り寄せて所定の形式があればその対策をするべきと痛感しました。
―何のテーマに変えたのですか?
Cさん:所得税法56条に変えました。Dさん:私は秋から対策を始めました。受験校は研究計画書と面接だけの大学を選び、研究計画書のテーマは10月頃に決めて11月くらいから書き始めました。私も航空機リース、租税回避のテーマが気になっていたのでそれについて書きました。研究計画書を書く際には黒須先生やチューターの方にアドバイスをいただき、何回も手直しをしていただきました。
立教や青学の面接の場合は研究計画書に沿った質問をされるので、研究計画書に沿った租税法の対策をするべきです。
―次に、①面接対策(口頭試問)について、②どのように情報収集をしたか、③秋入試を受けるために今の時期にやっておくべきこと、④仕事や大学・国家試験との兼ね合い・・・について教えてください。
Aさん:専修大学の面接は「租税回避とは何か」「脱税とはどう違うのか」など、結構突っ込まれる口頭試問形式です。この対策として自分の言葉で話せるように勉強をしました。友人や黒須先生にも手伝ってもらいながら面接の練習をしました。情報収集は黒須先生やチューターの方を通して行いました。大学院は教授との人間関係がとても重要になってきます。そのため、今の時期は本当に自分にあった大学院選びをするべきです。
―今の時期やっておくべきこととして「研究室訪問」は積極的にやっておくべきですね。実際に指導教授に会っておくことで、後の面接を有利に働かせることができますからね。
Bさん:明治大学の面接は「なぜうちの大学に決めたのか」などの基本的な質問が多く、経歴や研究計画書のウエイトが大きいと感じました。情報収集ですが、KALSではOB・OG会や定期的な飲み会を行っています。その席で実際に大学院に通っている先輩に話を聞いて情報収集をしました。
今の時期は、前述した方法(先輩に話を聞く) や研究室訪問、学校主催のイベントなどに足を運び、情報収集に徹するべきだと思います。
Cさん:社会人入試では、研究計画書と面接が重要だとよく言われます。面接の直前期には自分で想定問答集を作ってまとめました。黒須先生から過去に問答されたことを聞いていたので、それを参考にして作りました。専修大学の面接では教授陣が学者でしたので、「租税法律主義の内容を説明してください」などの租税法の総論の部分について聞かれました。
立教大学の場合は指導教授1名と税法とは関係のない教授2名での面接でした。質問内容は「通達は実務でどうやって使っているか」といった実務に関することと、研究計画書のテーマでもあった所得税について「所得税で気になる論点はあるか」ということを聞かれました。
今の時期にやるべきことは、研究計画書のテーマを書くための資料を探すことだと思います。
仕事と大学、国家試験との兼ね合いについてですが、これは時間をきちんと使い分けて、切り替えをうまくやるにつきます。
Dさん:青学の面接は税法の教授が1人、他の専門分野の教授が2人という形でした。必ず聞かれる質問として「青学の説明会には出席したか」ということを聞かれます。他には「仕事と大学院の両立はできるか」「仕事の調整はできるか」などです。
情報収集ですが、基本はKALSのOB・OGの方が残してくれた情報を参考にしました。また、青学に友人がいたのでそこからも情報を得ました。今の時期やっておくべきことはやはり、租税法の理解と研究計画書を詰めることだと思います。
仕事と大学との兼ね合いとしては、職場の方の理解を得ることが重要です。
―ちなみに、職場の上司の許可は事前に得ていたんですか?
Dさん:はい、得ていました。―ずいぶん理解のある上司だったんですね。それでは、現在の状況について教えてください。また、大学院卒業後の展望も含めて。
Aさん:私は大学院の授業を週6コマ、学部の授業を1コマ取っています。大学院1年目は、週3で学校に通っています。うちは研究がメインなので他と比べても忙しいほうですが、雰囲気はとても良く、教授とも飲みに行くほど仲が良いです。卒業後は税理士を目指しつつ実家の会社を接いで行きたいです。
―卒業に必要な単位数は?
☆受験生へのメッセージAさん:32単位です。
Bさん:明治は平日の夜6時55分から授業が始まり、10時に終わります。土曜日は朝の9時から授業があり、長い人で夜の9時10分まで授業が組まれている人もいます。グローバル・ビジネスは社会人大学院ということを掲げているため、社会人でも来られるということを前提としてカリキュラムを組んでいます。
卒業までに46単位必要で、年間に36単位までしか取れないと決まっています。私は前期で8コマ、後期で10コマ取り、前期は週3、後期は週4で学校に通いました。私の場合アルバイトもしていましたし、好きなこととの両立も可能ですので、特別忙しいと感じたことはありません。
将来は税理士試験を終えて会計事務所に勤められたらいいなと思っています。
Cさん:現在は週3日で授業を受けています。立教の場合は2コマ続けて同じ授業を取るので、前期で4単位、後期はまた違う授業で4単位という形で、卒業には30単位が必要になります。そのうち8単位がゼミです。ですので、22単位を合計6コマ取るということになります。
授業は夜の6時半から9時半までで、土曜日はゼミのみです。ゼミは通年あるかわりに隔週というのがとても助かっています。大学院生活は毎日が忙しいですが、その分、楽しさもあります。
卒業後は税理士になって、タイミングがあれば独立もしたいです。
Dさん:青学のカリキュラムは土日がなく、平日しかありません。時間は6時半〜8時、8時10分〜9時40分で、卒業までに30単位が必要です。1年で取れる単位が20単位と決められていて、残りの10単位を2年で取ります。そのため論文を書きながら前期で10単位を取るとなるとちょっと忙しいですね。
青学は税法の他に金融、労働法、知財などが学べるので色々な知識を吸収したい方にはおすすめです。
やはり授業が平日に集中しているので、日々の生活は忙しいです。社会人の方はどのように時間を取るのかを考えたほうがいいでしょうね。
卒業後はもちろん税理士になりたいです。
―最後にこれから受験される皆さんにアドバイスをお願いします。
Aさん:教授との人間関係をうまく築いていくのが大学院生活を送る上で一番重要です。今の時期から情報収集をして、どの大学院の教授がどのような学生を欲しているかを調べる必要があります。その学校、その教授によってかなり違ってくるので、その判別をするべきです。頑張ってください。
Bさん:他の大学もそうだと思いますが、明治としてはぜひ、やる気のある方に来てほしいですね。先生曰く実務経験がなくてもやる気があれば、現時点で能力がなくても選考するとおっしゃっていました。ぜひ、明治に来てください。
Cさん:研究計画書を作るのは大変ですが、そこを乗り越えれば合格に近づけます。面接の質問に1つ2つ答えられなくても合格できます。私がそうでしたから。皆さんも面接では緊張せずに挑んでください。
Dさん:一生懸命時間をかけて研究計画書を書けば、やる気と意気込みは伝わります。先生たちも最初から完璧なものは求めていませんから。大学院はいろいろ厳しい面もありますが、様々な出会いや世界の広がりを感じられる所です。私自身も大学院に入ったことで成長できたと感じています。皆さんも頑張ってくださいね。