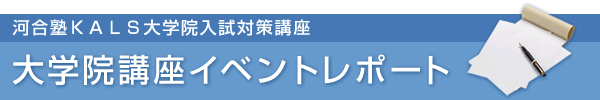日本大学大学院 経済学研究科 合格者
≪2011年5月21日に新宿校で実施した「合格者講演会」の模様を一部採録したものです。≫
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
合格者Aさん:日本大学大学院 経済学研究科
司会:河合塾KALS・黒須先生
黒須先生:みなさんこんにちは。これから税理士「税法」科目免除大学院の合格者講演会を始めさせていただきます。本日は社会人入試の合格者1名をお呼びしています。まずはじめに大学院を目指した理由、またはきっかけを教えてください。
Aさん:私は社会人入試で受検し、現在は日本大学大学院 経済学研究科の1年です。大学卒業後、一度就職をしました。27歳で税理士試験の簿記論と財務諸表論に合格し、その後は税法を何度か受験していましたが、なかなか合格できずにいました。しかし、何年か仕事をしていくうちに、職員という中途半端な形ではなく、やはり税理士になりたいという思いが強くなったのと同時に、付き合っていた彼女(現在の妻)から「あなたこのまま一生人に使われて過ごすの?」というキツイ一言を言われたのがきっかけとなり、35歳のときに本格的に税理士になろうと決めたのです。大学院に行けば、最短距離で確実に税理士になれるだろうという考えから、大学院を目指すことにしました。そして41歳の今、日本大学大学院に通って一生懸命勉強しています。
黒須先生:いつ頃から受験対策を取り始めましたか? また志望校の選定方法、決定理由を教えてください。
Aさん:私は国税徴収法に合格していましたので、税理士の試験を受ける必要がないため、時間が結構ありました。 KALSの授業は4月から始まるのですが、3月頃にはチューターの方に、あらかじめどんな本を読んだらいいか相談しており、そこで薦められた『税法入門』を3月半ばから一通り読みました。また、個人的にかなりお勧めなのですが、三木義一先生の『よくわかる税法入門』も読みました。こちらは税法に対する問題提起が非常に良く書かれているので、税に対する疑問がはっきりわかって読みやすかったです。
授業が始まってからは授業の予習・復習を行いながら、5月から7月にかけて、研究計画書のテーマ決めをしました。母校の大学で資料を集め、その資料を読み込みました。8月の終わりくらいには研究計画書が完成し、願書を提出、9月は面接対策を行いました。
志望校の選定ですが、確実に国税審議会を通る修士論文を、きちんと指導してくれる大学院でなければならないということが前提にありました。他には、過去何年かの実績が十分にあること、平日の夜間および土日の授業制度があること、職場や自宅から近いということがありました。これらを踏まえてチューターに相談したところ、高千穂大学、立教大学、日本大学、専修大学、文京学院大学を勧められました。
まずはこれらの大学院をインターネットで検索したあと、募集要項を取り寄せてじっくり調べました。すると日大の教授は国税庁の幹部の方が多く、税法でも主要の5科目の他に国税通則法や国税徴収法なども学べることを知りました。
9月の頭には実際に日大の藤井先生にアポを取り、直接会ってお話を伺ったところ、話もわかり易く、とても優しい印象を受けました。
最終的には高千穂以外の学校を受験し、立教以外は合格しましたが、教授がゼミで持っている人数、教授の人柄、授業内容、図書館の蔵書数を考慮した結果、日大に決めました。
黒須先生:KALSの講義以外の勉強方法と研究計画書について教えてください。
Aさん:私はKALSの講義以外では特に勉強はしていません。
私の研究計画書のテーマ決定は、みなさんの参考になるかどうかわかりませんが、一応お話しすると・・・授業中、先生が訴求立法の授業をやっていたときに、「これは研究計画書のテーマに最適です」とおっしゃっていたので、当時はよくわかりませんでしたが、これでいいや!と思い、このテーマに決めてしまいました。しかし授業の早い段階で訴求立法の話が出てきたので、余裕を持って研究計画書を作成することができました。研究計画書の作成には、そのテーマに興味があるかどうかも重要ですが、早い段階で取り掛かることも重要です。
黒須先生:口頭試問あるいは面接対策についてお願いします。
Aさん:研究計画書をきちんと作ることが一番の対策になります。ずさんな研究計画書では教授は最初から相手にしません。参考文献や参考文献の引用部分の書き方などがしっかりしていると、先生もニコニコして話を進めてくれます。
専修大学の研究計画書は、大学院側が指定する書き方で書かなければなりません。しかも手書きです。基本的な知識を求められることが多いので、KALSで配られる面接対策の本を参考にするのがいいと思います。
立教大学の先生は、面接当日まで研究計画書を読んでいません。その場で読み始め、素人が質問するように、少しとぼけて「これってどういう意味ですか?」とか「訴求立法をやって何の意味があるんですか?」などという質問をしてきます。立教の場合は、素人でもわかるような説明が必要です。
日本大学の場合は研究計画書の内容に結構つっこんで質問されるので、何を聞かれても答えられるようにしておく必要があります。ある程度文献を調べて、自分なりの結論を出しておけば大丈夫でしょう。他に受験の前には、ぜひ先生にお会いしておくべきです。そこでお話を伺ったり、研究計画書の内容についてお話を聞いたりしたほうがいいでしょう。結構手直ししてくれたりします。
黒須先生:次に大学院生活についてお聞かせください。
Aさん:まず研究室についてです。私の場合は非常勤の先生ですので、週一でしかいらっしゃらないため、ゼミの人数は4人です。常勤の先生の場合だと7〜8人と、多めに人数を設定していますが、非常勤の先生は少なく設定しています。
授業は税法中心です。専門学校で扱う部分もありますが、主に有名な判例が中心に出されるので、今の段階から予習・復習をしておくと勉強しやすいと思います。藤井先生の授業では実際にわからなくても、わかりやすく、ゆっくり、丁寧に解説してくださいます。
教科書は主に金子先生の『租税法』を使用しています。KALSで勉強していれば、ある程度理解した段階で大学院に進めるので、授業は理解しやすく、学びやすいでしょう。
仕事との両立ですが、私は現在、週三で大学院に通っています。火曜日と水曜日は18時から22時の授業を取っており、土曜日は10時40分から18時くらいまでの授業を取っています。私の場合、今年だけでゼミ以外の単位はすべて取得できる予定ですので、社会人の方でも両立は可能です。ただ、授業が18時から始まるので、早めに仕事を切り上げる必要のある方もいるかもしれません。
授業では出席を取る先生と取らない先生がいますが、基本的には授業に出席してまじめに勉強していれば単位は取れます。
黒須先生:最後にこれから受験するみなさんへのメッセージをお願いします。
Aさん:ここにいる皆さんも、おそらく税理士を目指しているかと思います。
KALSに入って勉強していれば、大学院に入るのもさほど難しくはないですし、入学してからも難しく感じることはないと思います。KALSの「税法演習」では、判例を詳しく見たり、研究計画書対策について、教えていただいたりする時間もあります。ぜひ「税法」と「税法演習」の両方を受講して万全の体制で臨んでください。この2つを受講していれば最短距離で大学院の受験までいけます!