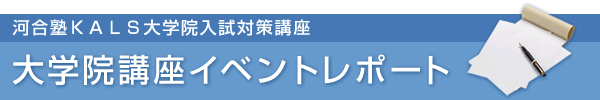● 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究科 / 拓殖大学大学院 商学研究科 /
専修大学大学院 商学研究科 合格者
● 国士舘大学大学院 法学研究科 / 立正大学大学院 法学研究科 /
日本大学大学院 法学研究科 合格者
● 日本大学大学院 経済学研究科 /
明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 合格者
● 立教大学大学院 経済学研究科 合格者
≪2011年10月23日に新宿校で実施した「合格者講演会」の模様を一部採録したものです。≫
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
合格者Aさん:横浜国立大学大学院 国際社会科学研究科(進学) /
拓殖大学大学院 商学研究科 /
専修大学大学院 商学研究科 合格
合格者Bさん:国士舘大学大学院 法学研究科(進学) /
立正大学大学院 法学研究科 /
日本大学大学院 法学研究科 合格
合格者Bさん:日本大学大学院 経済学研究科(進学) /
明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 合格
合格者Dさん:立教大学大学院 経済学研究科 合格
(司会:河合塾KALS・黒須先生)
黒須先生:まずは大学院を目指した動機・理由を教えてください。
Aさん(女性) :私が税理士の資格を目指したのはすごく最近のことです。大学時代は理工学部で応用科学を勉強していました。卒業後一度は就職したのですが、徐々に人に雇われて働くのではなく、自分で何かをしたいと思うようになりました。人と話すことが好き、数字が得意ということを活かして何か仕事がないかと探したとき、税理士に行き着いたのです。そして30歳を過ぎて会計事務所に就職しました。そこで2年ほど働いたときに今度は、税法だけ勉強していたのでは仕事にならないと気づき、大学院に入って民法や憲法などといった法律と言われるものを勉強しようと大学院を目指しました。
Bさん(男性) :私は大学3年生のときに税理士の勉強を始めました。できるだけ早く資格を取ろうと思い大学院への進学を決めました。
Cさん(女性) :税理士の勉強を始めたのは勢いでした。昔から英語の通訳をやっているのですが、正直言って人の言葉をしゃべるのに飽きてしまい、自分で何かを考えて主張していきたいと思うようになりました。また、高齢の父の仕事を手伝ってあげようという思いから簿記論と財務諸表論を勉強し始めたのですが、想像以上に難しく本気で勉強しようと大学院入試を考えました。
Dさん(男性) :実家が中古自動車販売店を営んでいるのですが、父が会計や経営に関する知識に欠けているため、私が補ってあげられたらいいなと思い税理士を目指すようになりました。最初は科目免除を受けて税理士になることに対して、ずっと後ろ向きのイメージがありました。しかし、私の周りにも何人か大学院に行っている人がいるのですが、話を聞いてみると、想像しているのとは違い税理士試験とはまた違った視点から租税を学べることを知りました。現在、昼間は会計事務所に勤務しており、夜は大学院の社会人コースに通っています。
黒須先生:次に受験のための準備期間、志望校の選定理由、勉強方法について教えてください。
Aさん:私は春入試で受験しました。勉強を始めた時期はKALSに入学した9月半ばからです。当時は租税法もわからなかったので、入門書からいろんな本を読みました。
志望校の選定ですが、いろいろ説明会に参加してみると他校では「うちに入れば必ず科目免除ができる」ということを強調していましたが、横浜国立大学は「しっかり勉強させる」ということを強調しており是非ここで勉強したいと思いました。
Bさん:私は9月入試でした。8月の税理士試験まではKALSでの授業の復習をする程度で、あとは税理士試験の勉強をしていました。試験が終わってから本格的に税法や英語を勉強し始めました。税法は黒須先生の授業を聴いて復習をしていれば問題は無いでしょう。
英語は大学時代に使っていた参考書を使って勉強すれば、大丈夫だと思います。
Cさん:税理士試験が終わった8月、ちょうど1年前からKALSで勉強を始めました。租税法については金子宏先生の租税法の本をきっちり抑えて、黒須先生の授業に出ていれば大学院入試には十分だと思います。
私には税法の知識が足りませんでしたので、民法、会社法、租税法、そしてそれらの周辺の法律をきっちり勉強したいと思っていました。大学院によってそれぞれ特色があり、日本大学経済学研究科の場合は所得税法、法人税法、会社法、民法のカリキュラムが充実しており、免除を受けられる確率が高いということで日本大学への進学を決めました。
Dさん:私も税理士試験が終わった後にKALSで勉強しました。
社会人でしたので交通の便、試験日程、友人が専修大学に通っていたことなどを踏まえた結果立教大学と専修大学に絞られました。対策ですが、私は研究計画書と口頭試問のみの大学を受けましたので、研究計画書を作りこむことに専念しました。口頭試問は想定問答集を作って対策を取りました。
黒須先生:では、肝心な研究計画書のテーマ設定から作成まで、口頭試問、面接対策についてお願いします。
Aさん:私の場合、受験した全ての大学で研究計画書について聞かれることはなかったので、参考になるかわかりませんが・・・。私は所得税法を勉強していたこともあり、そこからテーマを選ぼうと思いました。拓殖大学と横浜国立大学での口頭試問では専門的なことは聞かれませんでしたが、専修大学では金子先生の本で覚えたものから3問出題されました。
Bさん:私は当初、研究計画書のテーマを所得税法56条にしようと考えていたのですが、受講生の中で56条を選んでいる人が多かったため、推計課税に変更しました。
私が受験した大学では口頭試問はなく、面接は、研究計画書の概要、志望動機、大学での勉強、税理士試験の勉強について聞かれました。特に一般入試では「2年間で論文を書ききれる能力があるか」という所を見られているので、それを念頭において対策を取ったほうがいいでしょう。
Cさん:テーマは何でも大丈夫です。テーマが決まったら裁判所の判例やそれに関係する条文を集めます。TKCから評釈をダウンロードして学者、実務家などクオリティーの高い論文を集め、判例の整理をします。そのとき素人である私たちは、どちらの判決が良いか悪いかという判断は控えて、なぜその結果になったのか、その原因を考える作業にたくさん時間を費やした方がいいと思います。そしてたくさん掘り下げてください。その原因が研究テーマになると思います。
どこの面接でも聞かれたのは「なぜ本校なのか」「なぜ税理士なのか」という質問です。
日本大学では「5分程度で研究計画書の説明をしてください」と言われました。そこでもただ書いたものを暗記して読み上げるのではなく、研究計画書を提出してから面接までの間に自分がどれだけ考えたか、何を問題点としているのか、その問題点についてこれからどういう風にアプローチをしていくのかを中心に説明するほうがいいと思います。アピール時間が15分程度しかないので、いかに時間を有効に使って自分のやる気や考えていることを伝えるかが重要になります。
明治大学の面接ですが、こちらはいきなり「こんなものが欲しいんじゃないんだよね」と言われ、明治大学に入って何を勉強したいかという「学習計画書」が欲しいんだということを言われました。ですので、研究計画書については全く聞かれず、なぜ通訳なのに税理士を目指しているのかという世間話的な感じで終わってしまいました。
Dさん:研究計画書のテーマや内容は大学院に入ってから変えられるので、私は当時、研究計画書は大学院に受かるための道具だと割り切っていました。立教大学の研究計画書の場合は、黒須先生からいただいた研究計画書のサンプルの中から最もボリュームがあり、多少なりとも自分の興味があるものを選び、それをアレンジして作りました。しかしそれだけですと面接に対応できないので、参考文献を読みあさりました。
専修大学は少し変わっていて、マス目や書く内容が決まっています。専修大学を受ける方は早めに願書を取り寄せてください。したがって私が作った研究計画書では専修大学に対応できなかったため、そこから更に先生の下にも何度も通いながらアレンジしていきました。研究計画書というよりは学習計画書に近いと思います。どのように論文を作成していくかというものを作ったのですが、意外にこれが面接対策にもなったのです。
面接対策では是非みなさんにお勧めしたいことがあります。KALSには過去の面接内容が詳しく載っている「入試アンケート」というファイルがあるので、これは絶対に活用してください。私が受けた面接でも、そのファイルに書かれている質問内容が聞かれたので、あらかじめ見ておいて本当によかったと思っています。
黒須先生:次に皆さんの大学院生活について教えてください。
Aさん:横浜国立大学は土日休みで、授業は8時50分から17時45分の間にあります。同級生やドクターのかたは会社を経営していたり税理士として働いている方がほとんどなので、わからないところはすごく聞きやすいですし、勉強もしやすいです。ただ、土日含めほぼ毎日、一日中学校で勉強しているためアルバイトなどをする余裕はありません。
Bさん:国士舘大学の場合は土曜日に朝から夜まで授業があり、その他は平日に2コマ自分で授業を入れます。ゼミ生は社会人と学生の割合が7対3くらいで、私の指導教授である酒井先生は、生徒の考えを尊重し、またそれを伸ばしてくれるので、すごくやりがいのあるゼミです。酒井先生は独自に会計事務所に勤務している税理士の方を対象にしたセミナーを持っているのですが、そのセミナーの後に交流の場を設けてくださるので、他の事務所の方と知り合えるいい機会になっています。
Cさん:日本大学の場合、税理士試験を受けられる方には天国のような思いやりのある教授陣ばかりです。テストはなくレポートと出席率で決まるのですが、レポート提出も税理士試験後にしてくれます。そうは言っても授業、税理士試験の準備、通訳の仕事をこなすのは、結構大変ですが・・・。
Dさん:立教大学では松本敏郎教授の下で学んでいます。1年の前期は税法の基本的なことを学ぶほか判例研究をします。後期からは実際にテーマを見つけ出そうということで興味のある文献からテーマにしていきたいものを探っていきます。松本教授は元々、国税局長であり、現在は全国法人連合会でも税金の仕事をされているので、税に関する資料をたくさんお持ちのため、自分はこういうのに興味があると伝えるとその資料をUSBに入れて持ってきてくれたりします。
授業は租税に関するものが3コマあり、他は経営に関するものが多いです。
黒須先生:最後にこれから大学院を目指される方にメッセージをお願いします。
Aさん:大学院に入ってから気づいたことですが、研究計画書を作るときは判決文を読んで欲しいなと思います。私の場合、判例評釈ばかり読んで研究計画書を作ってしまったのですが、判決文の中には全部の情報が詰まっています。判例評釈は判決を読んだということを前提に学者の方たちが書かれているので、判決文を読んだ上で研究者の評釈を読んでください。
学校によって特色が様々ですので、学校説明会には積極的に参加して、わからないところは質問したり、自分の指導教授になる方と話してみたりすることが重要になります。学校選びは慎重に行ってください。
Bさん:情報は早めに入手しておくことです。私もそうだったのですが、行きたい大学のオープンキャンパスが終了している場合があるからです。研究計画書も大学によって形式が違いますので、早めに資料を入手して準備は早めに行ってください。
一般入試の場合は面接よりも筆記試験が重視されるので、しっかり答案用紙を埋めて頑張ってください。
Cさん:日本大学は倍率が大変高いようですが、人気が高いということで、受験者のレベルが高いのとは違います。ですから難しいと考える必要はありません。自分で問題点を見つけ出すところまでやっていただければ、ほぼ大丈夫ではないでしょうか。
面接では、自分なりに一生懸命考えて強くアピールしてください。
Dさん:立教大学は今年から小論文が導入されています。導入した理由は、文章作成能力があるか、意味の通る文が書けているかどうかをチェックするためだそうです。難しいことを求めているわけではないので、やはり今まで通り面接が最も重要になってきます。面接では第一印象で決まる場合があると聞いたことがあります。また、修士論文が書ける能力があるかどうかを見られるので、以前に論文を書いたことがあれば、それもアピールしたほうが合格率は上がると思います。