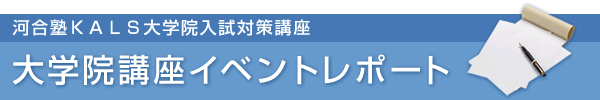●早稲田大学大学院 商学研究科 夜間主総合 /
早稲田大学大学院 ファイナンス研究科 /
青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 /
立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 /
(一昨年度)一橋大学大学院 商学研究科 合格者
●一橋大学大学院 商学研究科 合格者
●慶応義塾大学大学院 経営管理研究科 /
一橋大学大学院 商学研究科 合格者
≪2012年5月13日に新宿校で実施した「合格者講演会」の模様を一部採録したものです。≫
▼ガイダンス等イベントのお申込みはこちらから▼
早稲田大学大学院 商学研究科 夜間主総合(進学) /
早稲田大学大学院 ファイナンス研究科 /
青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 /
立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 /
(一昨年度)一橋大学大学院 商学研究科 合格・Aさん
はじめに
僕は2年間KALSに通いました。1年目は一橋大学に受かったのですが、会社に黙って受験をしていたので、休職許可が下りず、翌年リベンジし、早稲田大学に合格しました。
国内MBAを目指したきっかけ
大学時代法学部だったのですが、ゼミでマーケティングや経営に興味を持ちました。
受験をするにあたって、海外のMBAも検討しましたが、自費で行くとなると、2年間で1,500万くらいはかかると思うので、費用対効果を考え、国内MBAにしようと決めました。
MBAでの1週間
僕は社会人なので、日中は仕事をしています。会社には院に行くことは報告してあるので、残業などはないように業務配慮をしてもらっています。定時で上がり学校に行き、平日は19時から22時10分まで、二限分の授業があります。月・水・金・土曜日に授業があり、火・木曜日は授業はないですが、ないと言いつつもチームワークが入ります。周りの方も社会人なので集まるのが難しいのですが、無理にでも時間を作り、打ち合わせをするという生活をしています。土曜日は、一限から授業をとっています。一限は9時からあるので、9時から16時〜17時くらいまで勉強しています。日曜日は学校がないので、半日は遊び、半日はレポートや課題を作成し、リフレッシュする時間を作っています。
学校選びの3つのポイントとメッセージ
一点目は、レベルが高く、入学者数が多い大学院を選んでください。
MBAの生活は、教授から教わる部分が5割と、もしかしたらそれ以上かもしれませんが、残りは周りの方とのネットワーク形成だと思います。レベルが高くかつ入学者数が多ければそれだけのネットワークもできるということで一点目に挙げました。
二点目は、有名な先生がいるということです。無名な先生の講義はつまらないとは言いませんが、やはりある程度名が知られている先生の授業は実際に面白いです。
三点目は社会人の方限定になってしまいますが、夜間主にぜひチャレンジしてもらいたいです。早稲田大学は理論と実践の融合と言われたりしますが、MBAで学んだことを実際の会社でリアルタイムで応用することができます。結構ハードですが、社会人の方は働きながら学校に通い、他の皆が休んでいる時に勉強をするというMBAの醍醐味を味わっていただければと思います。
一橋大学大学院 商学研究科 合格・Bさん
はじめに
私は経営学部経営学科を卒業し、一橋大学大学院商学研究科経営学修士コース(以下HMBA)に進学しました。一昨年KALSに通い、現在マスター2年です。HMBAはM2からゼミに入るのですが、そこで現在修論を執筆中です。
なぜMBAか
私は大学4年の時に、転職サイトを運営しているベンチャー企業で半年間インターンをしました。その中で、体系的な戦略がなければ会社は成長しないということを感じました。私は一応経営学部だったので、自分で戦略を立てられるかと考えたのですが、学部時代に全く勉強していなかったので、そんなことできるはずもなく、悔しい思いをしました。そこで、経営についてもう少し深く勉強したいなという気持ちがで芽生えました。
もう一つの理由として、学部時代に一つのことに死ぬ気で打ち込んだことがないことにすごく悔いを覚えていました。死ぬ気でがんばる経験ができる場所、そういう意味でMBAという厳しい環境があるというのを知り興味を持ちました。私は、将来的に起業したいと考えています。経営者になるためには、現場で経験を積むのも一つですが、新卒としてそのまま一つの組織に入ると、組織の色に染まってしまうのではないか、大局的な視野を磨けないのではないかという危惧があり、経営者に必要な能力を最短コースで磨くためにも新卒でMBAに進学して、思考のプラットフォームや基礎的な知識をつけて、現場に出て磨いていきたいなと考えたので、新卒でMBAに進学しました。
情報収集
大学院受験は、情報戦だと感じています。大学院によって試験傾向も違いますし、そこに集まる人たちの性質も大変異なっています。私は一橋大学に入るつもりだけで受験対策をしていました。
具体的には、まず志望校の学生から情報を集めました。内部情報を知ることが雰囲気や試験対策をするうえで最も重要だと思ったので、少々狡い手なんですが、SNSなどを使い、運よく内部の一つ上の学年の方とコンタクトをとることができました。そこで実際の学校生活や試験対策を聞き、より入学後のイメージがつかめました。二つ目は大学の教授からの情報収集です。幸いにも経営学部でしたので、ゼミの先生に、大学院で組織論などを学びたいということをお伝えし、組織論を専門とされている教授をご紹介いただき、その教授から、最近の経営学の分野においてどういうトピックが流行っているのか、そのトピックを網羅するための参考文献などを聞きました。
勉強法と推薦書
4月からKALSの「国内MBA・MOT速習コース」を受講していました。
KALSの「MBA論述対策」では、毎週必ず一題宿題が出ます。その宿題はKALSの講師の方が添削してくださるのですが、テキストには他にも問題があり、その問題をこなしたいけれど一人でこなすだけでなく、誰かに添削をしてもらうのが一番いい方法だと考えました。そこで、宿題以外の問題は、週一回、大学の先生にご紹介いただいた教授の研究室に通って添削していただいていました。私は論述対策のテキストの問題はほとんど解いたと思います。
HMBAの要約問題の対策として日経新聞に「経済教室」というものが毎日掲載されているのですが、私はそれを400字程度で要約するという作業をやりました。コツは、3つの要点ポイントを最初は隠して自分で要約をし、そのポイントと照らし合わせて、漏れがないか、きちんと論点は得ているかを確認するようにしていました。
『日本語作文の技術』『ゼミナール 経営学入門』『知的複眼思考法』という本はおすすめです。HMBAの先生は日本語の文法にうるさく、例えば順接の「が」など、細かい日本語の作法にとても厳しいので、それができるだけでも他の受験生とは大分差がつくのではないかと思います。経営学の知識がない方は『ゼミナール 経営学入門』をさらっと読まれるといいと思いますし、『知的複眼思考法』は、ステレオタイプにとらわれずに自分なりの物の見方ができ、一歩レベルアップしたい方のためにいい本だなと思います。
英語対策ですが、結論からいうと私はKALSのテキスト以外はやっていません。テキストの問題を漏れなく解き、テキストに出ているテクニカルタームを全て網羅したことは有効だったと思います。実際に試験でもテクニカルタームはいっぱい出ていました。さらに単語力を強化したいという方は『速読速聴英単語』という本は経済トピックもあるのでそれを読んだり、単語を覚えるのもすごい有効だなと感じます。
MBAでの生活
HMBAの夏学期は、グループワークという、グループで何か作業をするということが非常に多いの、それに時間をとられます。あとは毎日の授業の予習復習です。自習室は24時間365日開いているので、夜も寝る間も惜しんでひたすら勉強しています。死ぬ気でがんばりたいと思って入った大学院なので、ぴったりの環境かなと考えています。
HMBAの授業は、基本的に日本語で行われているのでこれからのグローバル時代において英語力を心配される方もいるのかなと思いますが、最近は英語にも力を入れています。今年から英語の科目も増え、今私もとっていますが、グローバル・リーダーシップという授業で、リーダーシップ論について英語で学んでいます。
MBAで得られること・メッセージ
MBAで得られるものは、挙げるときりがないですが、学ぶ喜びというのを今一番感じています。知的好奇心も広まりますし、MBAに進学できてよかったと思います。普通であれば新卒は同じ学年の人としか知り合いになれないはずですが、自分が社会経験をしていなくても、同じ学年の社会人の方からいろいろな話を聞けて、就職の相談にも乗っていただけて、一生の仲間なんだなということを感じます。さらに、なかなか辛い生活なので、自分や周りの優秀な人たちに負けない、タフな精神力は鍛えられるのではないかなと考えています。ちなみに私は来年コンサルティング会社に就職します。すごく大変だと思いますが、MBAで得た経験は絶対いきてくると思うので自信を持って就職したいなと考えています。
院試はあくまでスタート地点であって、入った後に何をするかというので自分の過ごす2年間の価値が変わってくると思います。皆さんはまず院試を目指す段階だと思うので、その2年間をいろいろ考えたうえで、これから半年間を過ごしていただければ、きっと受かると思いますし、入った後にもいい経験が積めるのではないかと思います。
慶応義塾大学大学院 経営管理研究科(進学) /
一橋大学大学院 商学研究科 合格・Cさん
はじめに
現在慶應義塾大学大学院経営管理研究科(以下KBS)の1年です。去年の今頃、ちょうど仕事も5年くらいやっていて、MBAに行きたいと思い、海外か国内か、国内ならどこがあるのかなと検索していてKALSのこの講演会にいきあたりました。その後、KALSで勉強し、9月に一橋大学、10月にKBSの試験があり、両方とも運よく合格することができまして、会社は退職して、今はKBSに通学しております。
国内MBAを目指したきっかけ
私の実家は商売をやっています。それまでは全く関係ない会社に勤めていたのですが、ゆくゆくは実家に戻りたいと考えました。経営となると、現場の視点も、その一つ上の視点も非常に大事だなと思い、そこからMBAというものを意識し始めました。国外か国内かと考えましたが、私がやりたいのは日本の会社の経営なので、国内MBAに行くのが一番理解度が深まるかなと考えたのが最後の決め手でした。そこに至るまでにはKBSやHMBAなど、いろいろな先輩や卒業された方とコンタクトをとり、志望校を少しずつ決めていきました。
受験勉強について
受験勉強は、大体5月の中旬〜下旬くらいから始めました。勉強をするという習慣がそもそもなかったので、勉強したりしなかったり、あまりよくない生活をしてたのですが、次第に目標も明確化してきて、勉強するようになりました。ピークは多分8月9月で、仕事と睡眠以外はほとんど勉強していたと思います。
この国内MBAというのは偏差値が全くないので、KALSを受講しても、自分がどのポジションなのかも、受験者の中でどの位置にいるのかも最後までわかりません。まずは自分が行きたいと思う大学院の過去問を見るということが大事だと思います。HMBAだと問題量が非常に多いのですが、120分で解けばいいですし、KBSも問題量は比較的多いのですが、90分で解かないといけないとか、英語がどのくらい解けるのか、小論文はどのくらい書けるのか、なるべく早い段階で確認した方がいいと思います。
私はそもそもそんなに学力が高い方ではないですし、英語も仕事で扱ったこともほぼないですし、多分TOEICも500〜600点くらいだと思いますし、小論文もそもそも書いたことがない、そういうレベルからのスタートでした。とにかくKALSで与えられた宿題を毎週やってこなす、英語は出された次の予習範囲の勉強をして、次の授業に備えるということを繰り返していました。小論文は、最初は感覚で書いてしまいますが、それでは落とされてしまいます。起承転結など、書くスキルがあり、中身云々はあまり問われません。例えば東京電力を国営化した方がいいかという出題がされて、イエスでもノーでも構わないのですが、イエスならイエスを構築するロジックをいかに組み立てるかが大事なので、それをKALSで教えてもらいました。添削を出して直して出して直してというのを繰り返していたと思います。KALSでも体系的に教えてくれますが、バーバラミントの『考える技術・書く技術』という本は小論文におすすめです。小論文はとにかく質よりも量だと思います。いっぱい書いてKALSで教えてもらった形をしっかり身につけていくことかなと思います。
英語は、結構離れている方は、過去問を見た時点で驚愕すると思います。私の場合は英語があまり得意ではなかったので、ますます思ったのですが、単語がわからないと全く読めません。KBSやHMBAでは英語はあまり重要視されないのと思われがちなんですが、受かっている人たちの話を聞くと、みんな6〜7割くらいは解いていました。半分でギリギリ行けるかどうかぐらいだと思います。まず最初はKALSで先生が説明、解説してくれる英文のわからないところを翌週までに全部覚えてくるということをやっていました。ただ、それだけでは少し足りないので、単語集を一つ選んで、それを受験の前日くらいまでずっと覚えていました。日本語も一緒ですが、単語がわからないと理解できないので、とにかく単語を覚えることです。KBSの場合は、辞書持ち込み可ですが、辞書を見ている時間はありませんし、受験会場では辞書を開いている人はほとんどいません。単語は覚えましょう。
研究計画書は大切
研究計画書と面接は、極めて重要です。私は多分6月くらいに書いたのですが、9月までで20回くらい書き直しをしました。研究計画書と小論文は非常に似ていて、小論文はある議題に対していかにロジカルに答えるかですが、自分のやりたいことや、志望したことに対してクリティカルな解答をするのが研究計画書ですので、感想文とは訳が違います。私はKALSの内外問わずに国内MBAを受験する人とこの一年で会いましたが、うまくいかなかった人は、研究計画書を軽んじていたなという印象がありますので、これは手は抜かない方がいいと思います。KBSの場合は特によく見られます。もしこれからKALSに通われるのでしたら、人脈もできてくると思いますので、先輩や知り合いの人に見せるなど、なるべく客観的に自分のロジックを否定してもらい他の人の反響を聞くのは大事かなと思います。
KALS以外にやったこと
私も日経新聞の「経済教室」をやっていました。実際の試験でもちょうど同じくらいのサイズが出題され、内容も結構一緒です。考えるロジックも同じようなことを求められますので、月〜金曜日の朝あれを10分間読んで10分間でまとめるということを毎日やっていました。ポイントは毎日やることです。おそらくKALS以外でやっていたのはこれくらいだと思います。
進学について
仕事をされている人は全日制に行くのであれば、辞めるのか、夜間主に行くのであれば、続けるにしても業務負荷がありますので、よく考えた方がいいかなと思います。受験するという時点でも勉強時間を確保するというので会社に対してある程度見えない負荷をかけないといけないので、働きながらでもそれができる環境かどうか、ご自身の職場を振り返って考えられるのがいいと思います。働きながらモチベーションを維持しつづけるのは結構しんどいです。私はKBSとHMBAに受かったので、そこからも少し悩みましたが、最終的にはKALSの先生や、自分の家族に相談して決めました。家族など関係する人に受験や進学の意志を理解していただくというのも社会人としては大事なことだと思います。
国内MBAの生活とメッセージ
実際の院生活は私も1か月半くらいしかいませんので、まだわかりませんが、とにかく眠いです。KBSは9割くらいが社会人だと思います。学生は本当に少数です。授業はきついですが、やりたいことをできる環境というのは非常に幸せだなと思っています。
これから受験を検討される方へのメッセージですが、一番大事なことは一度決めたら振り向かないということかなと思います。このまま仕事を続けた方がメリットの場合もありますし、転職した方がいい方もわざわざ勉強する必要もないので、振り返るポイントは多いと思いますが、一度決めたことにはなるべく振り返らないでとりあえず勉強するというのは大事なことかなと思います。
アドバイスとしては、学生の方もそうですが、特に社会人の方は時間がないのをあえて言いますが、量は質を作るということです。安易に質を求めないことが、特に国内MBAの受験においてはポイントになると思います。