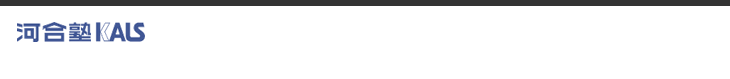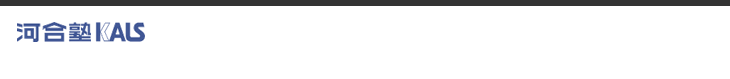|
論述力は大学院における最重要スキル
大学院入試において、論述力はさまざまな局面で必要とされます。筆記試験のみならず、その前段階の出願時にも、志望動機・志望理由、研究計画書、さらには学部卒業論文(もしくはその要旨)の提出が求められることも多々あります。
いずれの場合でも、専攻分野についての基本知識や自分なりの問題意識のみならず、それらを適切に表現する能力が必要不可欠です。つまり、大学院入学後の主な「仕事」である修士論文や学会論文執筆のための文章構成力が、入試の段階で問われているのです。
筆記試験で求められる論述
大学院入試の筆記試験では、よく「小論文」という科目が課せられます。また、専門科目の試験においても、論述形式による出題が大半を占めます。
まず、後者の専門論述の場合は、当然、専攻分野についての知識が必要となります。いわゆる語句説明であれば、①概念を提唱した人物の名前②その概念の定義 ③具体例 ④その概念の学史的位置づけ、あるいはその後の展開などの内容を盛り込んで、簡潔に整理しなくてはいけません。また、学説上の重要な論点についての意見や、入学後の研究テーマについて論述を求められることもあります。
一方、前者の「小論文」という科目では、(必ずしも専門分野の知識ではなく)一般的な問題意識や文章構成力自体が判断されることになります。たとえば、 少子高齢化、ボランティア活動、インフォームド・コンセント、テロ、戦争、ドメスティック・バイオレンス、多文化主義、グローバリゼーション、少年法、司法制度改革、介護問題など、近年話題のテーマ(時事問題)による出題が想定されます。対策としては、日頃からの新聞記事などへの目配りとともに、自分なりの問題意識や専門領域と関連づけて論じるテクニックを身につけておくとよいでしょう。
ただし、「小論文」という科目名であっても、実質的には(一般的な問題意識ではなく)専門分野についての知識等が問われる場合もあります。事前に志望大学の過去問分析をしておくことは不可欠です。
大学院入試における論述問題は上記の2種におおまかに分けられますが、両者に共通して大学院の論述で求められていることは何でしょうか。多くの方は、専門知識をできるだけたくさん見せることである、と思うでしょう。また、いかにもアカデミックじみた形式ばった表現が好まれると思う人も多いかもしれません。しかし、これらはいずれも誤りです。大学院の論述だからといって、アカデミックな雰囲気を出そうとして、やたらと晦渋な硬い表現を多用するのは好ましくありません。修士課程の試験では、採点者は一度に何人もの答案を読まなければなりません。一人の答案を読むために割く時間は当然限られてきます。そのため、分かりやすい文章を書くことが望ましいです。そのほうが採点者の印象はよいでしょう。
分かりやすさというのは、表現上の問題だけではありません。一つ一つの文章がわかりやすくても、構成が整っていなければ、全体として何が言いたいのか分からなくなります。
そのためには論理的に書くことが大切です。
論理的な文章と言うと、何か硬くて形式ばった文章、厳密な推論規則に則って展開された文章というイメージを抱く人々が多いですが、必ずしもそのようなものを意味しません。論理的とは、一言で言うと、首尾一貫していることを言います。そのためにも一つの論点で論じていくのがベストです。一つの論点で論じていくほうが、自分の主張が明確に伝わりやすく、分かりやすくなるからです。つまり、論述の最初から最後まで同じテーマ、問題意識で論じていくこと、これこそが首尾一貫性です。
もちろん、分かりやすいというだけではいけません。その上で内容のある論述を心がけます。そのような内容は自分が普段どれだけものを考えているかによって決まります。その過程で、いろいろな知識を蓄えておけば、それだけ見せる内容が充実していきます。しかし、論述試験で大切なのは、知識を見せることだけではありません。「自分はこんなことも知っている」とたくさんの専門用語をズラズラ並べるだけでは、論述にはなりません。基本的に「知識ひけらかし」型の論述は採点者が一番嫌います。そのような論述は決まって中身がないからです。また上述の首尾一貫性にも反します。まずは、テーマや論点を一つに絞って、その上で、その展開に必要な知識を援用するようにしましょう。
大学院入試論述攻略法
Iネタ集め
小論文を書くにはもちろんネタ、材料がなければなりませんが、それはどこから仕入れるのでしょうか。もちろん自分の専門であるというのは言うまでもありません。しかし、学科によってはそれだけでは不十分な場合があります。とりわけ、政治・経済・社会学を専攻している人は、時事的問題が出題される頻度が高いので、必ず新聞はチェックしてください。中でも社説は有効です。社説は、そのときの時事的話題を扱っていますし、社説の構成そのものが小論文の構成に大変近いからです。
II実際に書く
一番大事なのは、実際に小論文を書いてみることです。自分で考えることと、それを書くということの間には大きなギャップが存在します。書くというのは、相手に自分の考えを伝えるということです。自分の頭の中だけで考えて分かっているというだけでは駄目です。
自分が書いた小論文を、客観的に評価するのは大変困難です。一人で書いていると、自分の論文を批判的に見ることができないので、どうしてもひとりよがりになりがちです。そこで、第三者に実際に添削してもらう必要があります。そのためには先輩に見てもらうのもいいですし、予備校などを利用して小論文のプロに添削してもらえればもっとも効果的です。彼らは自分では発見できない小論文のミスを的確に指摘することができます。
III 実践~小論文の書き方(テーマ型小論文の場合)
それではここで実際に、小論文の実例を例にとり、小論文の書き方について説明します。
小論文には大きく分けて、課題文型とテーマ型と資料型の3つがありますが、ここではテーマ型を例にとって小論文の書き方の基本を説明していきます。
『課題: 携帯電話の功罪について論ぜよ。(800字程度)』
論述例
近年、携帯電話が大いに普及している。それは、携帯電話には、さまざまなメリットがあるからだ。たとえば、知人と外で連絡を取り合うときに、携帯電話によって、自分の居場所を知らせることができる。これによって、待ち合わせのトラブルがかなり解消されることになった。最近では、親が防犯のために、子どもに携帯電話を持たせるケースが増えている。子どもが事件に巻き込まれそうになったら、携帯電話を使って、親か警察に連絡するため、ということだ。以下、携帯電話が防犯にとって効果的かどうか論じていくことにする。
ニュースなどでは、子どもたちが性犯罪などの犯罪に巻き込まれるケースが頻繁に報道されている。そのため親が過敏になっているのであろう。しかし、その携帯電話が逆に子どもを犯罪に巻き込むケースがあることも否定できない。子どもが携帯電話で出会い系サイトなどの有害サイトにアクセスして、被害に遭うケースもある。さらに、子どものほうが、携帯電話から有害情報を仕入れて、犯罪を起こすケースもある。
もちろん、携帯電話そのものが悪いというのではない。むしろ、上の問題は使う側の意識の問題である。携帯電話の便利さが人間の心に油断を生じさせているのである。その便利さによって、親は過剰に安心してしまい、セキュリティーの意識がかえって甘くなる。また、子どもはその便利さを十分理解せず、悪用してしまうのだ。携帯電話を与えれば、子どもに対する責任を果たしたなどと思い違いをしている。このような、親たちの「ものまかせ」の姿勢が防犯にとって一番良くない。防犯にとって一番大事なのは、最終的に自分の身を守るのは道具ではなく、自分であるという強固な防犯意識である。親は責任を持って、子どもの防犯意識を普段から高めておく努力をすべきである。 |
|
論述の基本は首尾一貫性です。一つの論題を掘り下げて論じるのが理想です。
課題は、携帯電話の功罪について論じさせるものです。このテーマについてもいろいろな論点がありますが、なるべく一つを取り上げるべきです。ここでは、携帯電話の功罪を防犯という観点のみから論じています。こうすることで、論述にまとまりと緊密性が出てきます。他の論点、たとえば、携帯電話による文章作成能力の低下などは、この際無視してしまって構わないわけです。
さらに、大学院レベルの小論文では、問題提起をして、それに対して解決を与えるという論述の進め方が求められます。これが、研究の最も基本的なパターンだからです。ここでは、携帯電話がもたらす犯罪が問題であり、後の論述がこれに対する解決策になっています。また、このような論述の進め方は、首尾一貫性を持たせるためにも大変効果的です。問題提起をした後は、その解決に向けてひたすら議論を進めていけばよいからです。

小論文をこのパターンで書く習慣を身につけましょう。
|