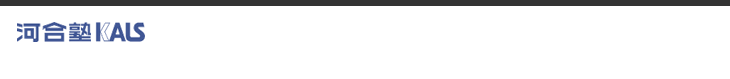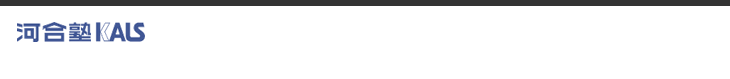臨床心理士になるためには、「財団法人 日本臨床心理士資格認定協会」が実施する資格試験を受験することとなります。この受験資格を得るためには、同協会が指定している大学院を修了しなければなりません。注意すべきことは、大学院の心理学系の研究科のすべてが、指定されているとは限らないということです。特定大学の特定専攻(コース)が指定されていますので、出願時には注意しましょう。
入試科目について
心理系大学院の入試科目は、全て交付、(1)語学(主に英語) (2)専門科目(心理学) (3)小論文の全て又はいずれかが筆記試験で、加えて、(4)面接試験が課せられます。また、出願時に提出する研究計画書なども重要な選考要素となります。
一般入試の場合、筆記試験科目として、英語と専門科目(心理学)が課されることがほとんどです。小論文試験のみを行うところは、あまりありません。一方、社会人入試の場合、筆記試験科目として、小論文を課されることが多いようです。その代わりに英語が免除されたり、一般入試とは別の少しやさしい英語が出題されたり、少しやさしい専門科目(心理学)が出題されたりと、社会人への配慮をしているところも多いようです。
また、社会人入試のほかに、心理臨床に携わる職務に規定の経験年数を満たしている方に対して、「社会人特別選抜」という試験を導入している大学院もあります。この入試でも、前述のような免除や、研究発表論文の提出によって試験科目が免除になるなど、同様の配慮が見られます。
志望校の決定
志望校は、できるだけ早く決めたほうがよいでしょう。志望校の出題科目、さらには出題傾向を調べ、学習計画を立てる必要があるからです。
志望校は、研究テーマで決めるのが一般的。自分が研究したいテーマを指導してくれる先生がどの大学院にいるのかを、まず調べてください。また、地理的な条件や学費の問題など一定の制限がある場合は、それらも考慮してください。
臨床心理士を目指して心理系大学院に進学しようとする方は、その大学院が指定校であることが絶対的な条件です。
志望校を1校に絞る必要はありません。受験料の関係もありますが、2〜3校程度、併願が一般的だと言えます。また、大学の学部入試と違って、大学院入試の試験内容は、学校ごとに色濃く個性が出ているものです。そこで、過去問を見て自分との“相性”を調べた上で、実際の出願先を決定するのもよいでしょう。なお、学部入試と異なり、大学の知名度と受験の難易度に相関関係は必ずしもありません。
志望校が決まったら、募集要項を入手して試験科目・出願条件などをチェックしてください。入手先や入手方法は、書店で市販されている『大学院案内』といった書籍や大学のホームページで簡単に調べられます。とりわけ、社会人入試で受ける方は、社会人の定義が大学院によって異なりますので、自分がその大学院で社会人に該当するかどうかを必ず確認してください。 同時に、志望校の過去問も取り寄せ、具体的な出題傾向を把握しましょう。過去問はほとんどの大学院で公開されていますので、大学のホームページや大学院の事務局に問い合わせて下さい。
ちなみに、指定校には第1種と第2種とありますが、第1種の場合は大学院終了後すぐその年の臨床心理士資格試験を受けることができ、第2種の場合は終了後1年以上の実習が必要とう違いがあります。
|