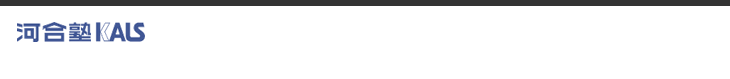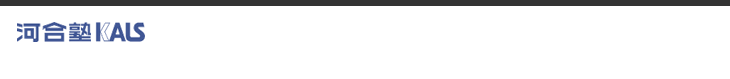|
研究計画書の対策
研究計画書(学習計画書など呼び方は様々)とは、修士論文として考えている“研究構想書”であり、ほとんどすべての大学院で出願時に必要となります。研究計画書には、タイトルを初めとして、研究の目的や仮説、方法などを書く必要があります。
心理系の学部・学科から心理系大学院への進学を考えている場合は、卒論の延長で書くことが一般的です。一方、社会人・他学部出身の場合は、新たに心理系の研究計画を立てることになります。このような心理学を学習していない方が心理系大学院を目指す際には、何らかのきっかけがあったはずので、研究テーマとしてはそれを煮詰めていくことが多いです。
研究計画書には自分の研究の仮説の根拠となる理論が必要です。卒論の延長で書く場合は、卒論を書く段階で、すでに先行研究の論文などを読んでいるので、それを使うことができます。しかし、新たに研究計画書を書く場合、その研究の基盤にするための先行研究論文を読む必要があります。したがって、この論文を読む時間がかなりかかることを計算に入れた上で、作成スケジュールを立てなければなりません。
心理学の論文と他の学問の論文では、書き方の法則などが異なります。とくに、他学部で論文を書いた方が心理系大学院を志望する場合、まずそのギャップを理解しなければなりません。この意味からも、できるだけ早く研究テーマを選定し、早く先行研究の論文を読み始めてください。
面接について
大学院入試の大多数が、一次試験(筆記試験)の合格者に二次試験として面接を課しています。その面接の形態・内容はさまざまですが、想定される質問としては、(1)研究計画書について (2)(社会人であればとくに)これまでの経験や心理学を志した動機について、などを聞かれることが多いようです。一方で、研究計画書については、まったく質問されなかったケースもあります。
大学院入試では、筆記試験の段階である程度の順位がつけられていることでしょう。したがって、明らかな上位数名は、確認程度の面接で済むこともあるようです。「ほのぼのしていて、雑談のようだった」という合格者の声も聞いたことがあります。ただ、多くの受験生は合格ラインぎりぎりのはずで、何名もの候補者がひしめき合っている状態の中にいるはずです。そこから数名を選抜するわけですから、当然、質問は厳しいものになることでしょう。
研究計画書をはじめ、これまでの経験を含めた内容的なものから、社会人であれば働きながら本当に修了時まで続けられるのか、その覚悟までをも聞いてくることもあります。また、学校によっては、“圧迫面接”のところもあるようです。たとえ厳しい面接であっても、それなりに対応できるよう事前準備が必要です。なお、言うまでもありませんが、大学院入学に対する熱意を示すためには、その大学院について多少なりとも調べ、知っておいたほうがよいでしょう。
|