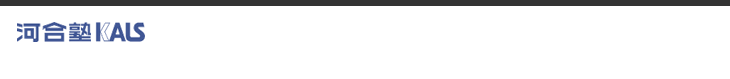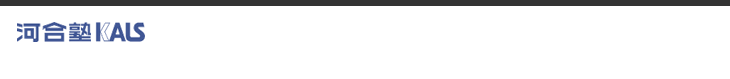法学研究科の筆記試験
法学研究科の筆記試験は、大きく3つのパターンに分けることができるでしょう。それは、(1)専門科目を2科目(英語の代用として専門科目を選択した場合も含む)解かなければならない、(2)専門科目を1科目解かなければならない、(3)専門科目1科目と英語を解かなければならない。そして、(3)が一般的なパターンであるように思います。
また、試験科目は“税法は必修”(ご自身の専攻する科目は必修であることがほとんどです)の可能性があります。したがって、専門科目の入試対策としては、税法(憲法、民法、商法等税法に関連する領域も含め)+英語を中心とし、志望校の入試形態に合わせ、他の専門科目1科目を勉強することが望ましいと思います。
法律科目は学習範囲が広いものが多いですが、大学院ごとの過去問を見ると、それぞれ特定分野に絞って出題されている傾向があります。ですから、出題傾向をしっかり読み取り、効率よく勉強しましょう。
英語に関しては、一般的な大学院同様、全文和訳、下線部和訳、全文要約等の読解問題が主流です。出題される英文の内容は、法学・政治学系のものとなります。構文としてはさほど難しくはありませんので、テクニカルタームの学習や内容の読み取りを中心に入試対策を進めてください。
経済学研究科の筆記試験
経済学研究科の筆記試験は、経済学(大学院によっては税法や会計学でも受験可もあります)と英語が出題されるところがほとんどです。
専門科目である経済学は、ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学等細かく分類し、出題されています。これも出題傾向を読み取り、効率のよい勉強を行ってください。税法を中心に勉強されている方は、財政学に絞って勉強することも良いかもしれません。志望とする大学院の出題傾向から判断してみてください。
また、英語に関しては、前述の法学研究科と同じく読解中心ですが、その出題される英文の内容が経済系のものとなります。
商学研究科または経営学研究科の筆記試験
商学研究科または経営学研究科の筆記試験は、経営学、会計学、商学(大学院によっては税法や経済学が出題される場合もあります)の専門科目と英語が出題されることがほとんどです。
この研究科を受験される方で、税理士試験の簿記論、財務諸表論について勉強・受験経験がある場合、専門科目の入試対策は比較的容易だと思います。それは、税理士試験の財務諸表論の理論の知識が、そのまま大学院入試の専門試験対策に流用できるからです。時間的に余裕がある分、英語の勉強にも集中できます。ただし、入学後においては、修士論文の内容が「税法」に関するものになりますので、税法の勉強も必要になります。
なお、英語に関しては、他の研究科と同様に読解中心で、その内容は経営系の英文となります。
以上、筆記試験について説明してきましたが、どの研究科でも、必ず出題傾向というものがあります。事前に過去問を入手し、しっかりと対策を練るようにしてください。
|