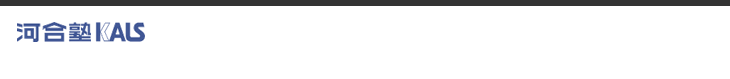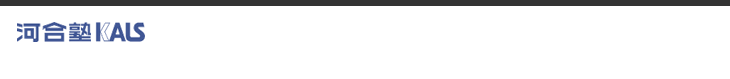|
理系の特色
理系とは、人間とそれをとりまく様々な自然現象のメカニズムの解明に始まり、現在では様々な応用分野も発展し、一口に理系と言ってもその内容は非常に多岐にわたります。理系の研究の特徴の一つとして、実証的・客観的であることが挙げられます。実際に測定したデータによって説明がなされ、客観的に理解されるものでなくてはなりません。他人を納得させるためには、何時間も議論を尽くすよりもまずは信頼に足るデータを示すこと。こういったことが暗黙の了解として進められているのが、理系の研究分野の特色です。
理系の学問分野
理系には理学、工学、医学、薬学、農学など様々な分野があり、各分野は細分化、多様化の傾向にある一方で、これらの区分は便宜的なものにすぎない、という一面もあります。実際、ある分野の専門的な研究を行うには他分野の基礎知識がたくさん必要になります。
また、例えば基礎科学と応用科学というように分類することもできます。理学は基礎科学、その他の分野は応用科学の色合いが強いですが、もちろんこれは一般的な傾向で、例外もあります。基礎科学では一般に新規性が大変重要です。一方、応用科学は新しければよいというものではなく、社会が求めるものを敏感に察知し、それに合ったものを迅速に提供することが大切です。
理系の各分野が相互に強く関連しているように、理系の研究の多くが人々の豊かな暮らしと持続的な発展のために進められていることを考えれば、文系と理系もまた、強いつながりを持っているといえるでしょう。
学際領域の発展
上記のように理系には様々な学問分野があり、それぞれの分野は細分化される傾向にあります。しかし、一方で近年、多くの学際領域が発展し、細分化とは逆の総合化も促進されています。理系の学問分野も、時代のニーズに合うように作りかえられているのです。実際に大学院で研究を進めてみると、様々な場面で他分野の基礎知識が必要になります。自分の専門にとらわれない、広い視野を持っておくことが大切です。学際領域の発展は、しばしば新しい学問分野を出現させます。ニュースや新聞、そして大学での勉強から、それぞれの分野での最新の動向を学び、自分が何を研究したいのか、じっくりと考えてみてください。
|