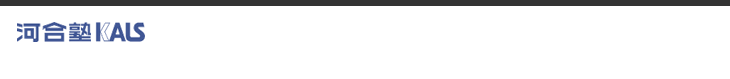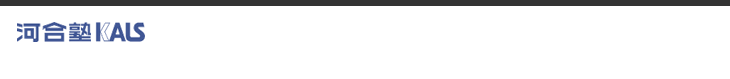理系の研究計画、研究論文は、分野による違いもいくらかありますが、概ね以下に述べるような形式で検討されます。理系の分野で研究や教育に携わっている先生方は日々このような思考を繰り返しており、いわばお決まりのルールのようなものです。研究計画書作成、研究室訪問、面接、いずれの時にも自分の研究計画を伝える時には、この形式に従うと、読んだり聞いたりするほうも非常に理解しやすく、印象もよくなります。
研究計画書のフォーマット
◆導入(Introduction)
自分が取り組もうとしている研究の研究背景、特に過去に行われた類似の研究について簡潔にまとめます。特に基礎研究では新規性が重要です。すでに誰かがやってしまった研究の反復にならないよう、ここできちんとチェックすることが必要です。また、なぜ自分がこういった研究に取り組みたいのか、なぜ大学院では学部学生時代と大きく異なる分野に取り組みたいのかなどについてもここで説明しましょう。
|
◆仮説、研究目的(Assumption、Purpose)
これらの項目は導入の部分に含められることも多いですが、独立した項目として述べられることもあります。科学研究の基本は仮説を立て、実験や調査によってそれを検証するプロセスです。自分がどのような仮説を持っているのかについて考えておく必要があります。それに基づき、自分の研究は何を明らかにすることが目的なのか、その研究を進めることにどのような意義があるのかなどについて整理します。
|
◆材料と方法(Materials and Methods)
どのような材料、試料を研究対象とするのか、又は調査対象地域はどこなのか、そしてそれらをどのような手法で、又はどのような分析機械を用いて解析するのかなどについて説明します。特殊な機械や非常に高価な分析機器などは特定の大学しか所持していないこともありますので、できる限り研究室訪問などの時に確認しておきましょう。
|
◆結果(Results)、考察(Discussion)、結論(Conclusion)
研究で得られた結果をまとめ、それを過去の研究で得られている知見などと比較して考察し、結論を導きます。この部分は、研究計画の段階で詳細に述べることはできませんが、上記の仮説とも関連させ、どのような結果が得られそうか、ある程度予測しておきましょう。しかし、研究する前から結果が分かっているのならあまり研究する意義が大きいとは言えません。予想外の結果が出るかもしれない、実験は失敗するかもしれない、それでもやってみたい、というような挑戦的な気持ちを持っていた方が良いでしょう。
|
理系の研究の構成は以上のようになっています。しかし、例えば面接のとき、「研究目的は何ですか?」、「研究材料は何ですか?」というような聞き方をされるとは限りません。あまり上記の形式にとらわれすぎないように注意しましょう。
研究計画の要旨も必要
研究計画を他人に伝える際に、もう一つとても重要なことがあります。それは研究全体を総括して簡潔にまとめた要旨(Abstract、Summary)を書ける(話せる)ようにしておくことです。要旨がうまくまとまっていると読む(聞く)方も研究内容を理解しようという意欲がわいてくるものです。要旨は、研究計画書、研究成果報告書などでは最上段につけられることが多いですが、実際に書くのは書類をまとめる最終段階にしたほうがよいと思います。
全体を通して注意すべき点は、不要な重複や無駄な記述をなるべく省き、簡潔にまとめることです。また、想像に終わってしまうような内容ではなく、限られた期間内に実現可能な計画を立てることです。そういった点では、1年目に何をする、2年目に何をするというような年次計画を考えることも有効です。研究計画の段階では想像の部分が加わってくるのは当然ですか、ここを、単なる空想ではなく先行研究に基づく予測として説得力を持たせることが大切です。
|