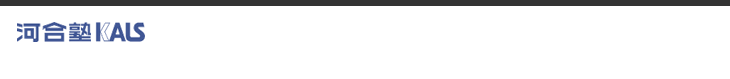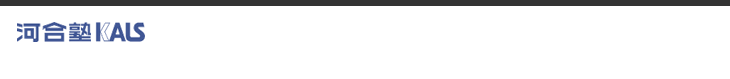|
募集要項で情報収集
大学院入試を突破するためには、まず、きちんとした計画を立てることが大切です。
一般には、理系大学院入試は夏期に行われることが多く、大学によっては秋期の入試が行われたり、2月ころに2次募集が実施されることもあります。改組や再編はしばしば行われます。試験日程等についてはインターネットや電話で必ず、当該年度の募集要項が発表され次第、再確認して下さい。
志望校は1〜3校
志望校は、最終的には1-3校に絞るのが一般的です。1校に絞り、もし受からなければ次年度にもう一度同じ大学を受験するという人もいますが、滑り止めを 1校受けて2校くらいに絞る人が多いようです。志望校の組み合わせには試験科目なども関係してきますし、最終的には研究室訪問を行ってから決定するのがよいでしょう。
21世紀COEプログラム
「魅力ある大学院教育」イニシアチブを大学院選択の目安に
2004年度より、国立大学は、国立ではなく国立大学法人となり、大学としての個性や特色を重視するようになってきました。それに伴い、国からの大学に対する予算の配分の仕方も変化してきました。理系の場合には特に、その研究推進のためにはしばしば非常に多くの予算を必要とするため、大学職員だけではなく、学生にとっても無関心ではいられない問題です。
21世紀COEプログラム(center of excellence 卓越した研究拠点)は、理系、文系を含めてそれぞれの学問分野で世界レベルの研究、又は発展する可能性のある研究を選抜し、それに対して国が原則として5年間、大型の研究教育のための予算を投入しているものです。現在、多くの大学では、どのような分野でいくつのCOEが採択されているかがホームページなどに掲載されています。採択されていれば、その大学はその分野においては日本のトップレベルにあることを示す一つの目安になります。
また、COEプログラムとは別に、2005年10月には、文部科学省が独創的な大学院教育を支援する事業「魅力ある大学院教育」イニシアチブを発表しています。これらはそれぞれの大学の研究教育活動が対外的にどのように評価されているかを知るには、非常に有益な指標となるでしょう。
研究室訪問は必須!
多くの大学では大学院入試に先立ち、オープンキャンパス(学校説明会)が行われています。実際に訪問してみることにより、様々な情報が得られるでしょう。試験日程や試験科目と並び、オープンキャンパスなどの情報もインターネットなどを用いて細かく確認しておく必要があります。
また、志望する大学や研究室がかなり絞れてきた段階で、研究室訪問を行う必要もあります。ここでは特に、自分がやりたいと思っている研究が実際にやれるかどうかをよく確認してくる必要があります。理系の場合、どういった研究ができるかは、特殊な分析機械や研究設備の有無に制限されることもありますので注意が必要です。また、先生によっては「いくつか研究テーマを提示しますので、この中からどれか選んでやってもらうことができますか?」という提案をするかもしれません。
研究活動はしばしばチームを組んで行いますので、その中で与えられた役割(研究テーマ)を果たすという研究の進め方を求められることもあります。一方で、学生の自主性を重視してかなりの部分まで学生自身に研究テーマを考えさせる先生もいます。いずれ、一度研究室を訪問して志望する研究室の先生と話しをすることは理系の場合には必須です。同じ年に多くの学生が志願すれば、全員の受け入れが難しくなるという現実的な問題もあります。しかし、たとえやりたい研究がそこではできないとわかったとしても、別な先生を紹介してもらえるかもしれません。また、研究室の大学院生とも話しができれば、それもたいへん参考になるでしょう。
|