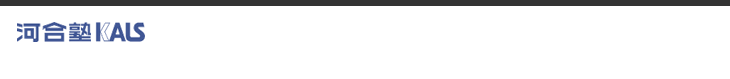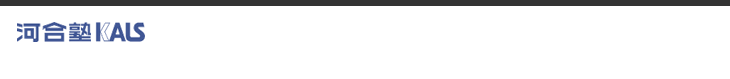|
英語が合否を分ける
よく知られているように、理系大学院入試では英語の試験が非常に重視されています。つまり、それだけ入学後の研究活動において英語での読み書き(時には会話)の能力が必要になるということです。ほとんどの大学では英語が試験科目に含められていますので、英語の勉強は志望校を決定するかなり前から始めてよいでしょう。実際、英語の試験は短期間の詰め込み学習では突破できません。原則として、少しでも多くの時間をかけた人の勝ちと考えてよいでしょう。しかし、もちろん勉強の能率や工夫の仕方でも差がつきます。では、どんな工夫をすればよいでしょうか
理系英語の学習法
大学入試と大学院入試で課せられる英語の試験とではだいぶ性質が異なります。
まず、大学院入試では単語や構文を読み取る力よりも文章読解力や作文力が求められます。また、英語の質が異なります。つまり、当然ですが、理系大学院入試では理系英語、科学英語の読み書きの力が必要となります。
では、こういった理系特有の英語になじんで行くためにはどのような工夫をしたらよいでしょうか?多くの人は、大学のゼミなどで専門的な英語の論文を読む機会を持つと思いますが、科学に関する最新の知見をレポートしているこれらの論文の読解を、「難しい…」と思うのではないでしょうか。そういった場合には、自分でいろいろなところからやさしい理系英語を探してくる必要があります。
実際、大学院入試ではあまり難解な英文は出題されません。また、あまりに専門的な英単語には普通、日本語でその意味が付記してありますし、大学によっては試験の際に辞書の持込みを許可している場合があります。つまり、ポイントは、基礎的な理系英語、専門に特殊化しすぎていないオーソドックスな理系英語を探してきて、それを読みこなすことです。しかし、学部学生がこれを自力で行うことは決して容易ではないでしょう。そういった意味では予備校などで使っている英語のテキストは最良の教科書です。
理系英語と他分野の英語の違い
さて、理系英語、科学英語を他分野の英語と比較したときにどのような違いがあるかお分かりでしょうか?
まず、自然科学に関する単語が頻出することが、当然ながら特色の一つとして挙げられます。ですから基礎的な単語はしっかりと身につけておく必要があります。(例:artificialを「芸術的な」ではなく「人工的な」という意味) 理系英語のもう一つの特徴は、いわゆる話し言葉(口語)調で書かれた文章よりも、むしろ学術的に書かれた文章が多いことです。(例:do(する、行う)よりもconduct、carry out(実行する)やperform(遂行する)という言い回しが好まれる)
以上のように、理系英語で頻出する単語や言い回しについてはその類義語や対義語に関する知識を深めておくことも必要です。高度に専門的な単語にそれほど注意する必要はない分、頻出する単語やその用法については熟知しておく必要があります。(例:「これまでに… という知見が明らかにされてきた」→「これまでに」にはso far、until now、up to now、up to the present。nowは口語的な単語と書きましたが、複合語にすればそのニュアンスも違ってきます。「知見」はknowledgeです。「明らかにされてきた」はreveal、clarify、make clear、apparently show、clearly indicateなどを受け身の完了形で。一例を挙げるならThe knowledge on the … has been revealed so far. となります。)
このように、日本語の語順と英単語の順序が必ずしも一致しないことにも注意を要します。ニュアンスは違ってきますが、find、discoverなどを用いても類似の表現ができます。逆に、「知られていない」、「知見が不足している」というような場合にはunknown、lack、devoid、 dearth、scarceなどを用いて実に様々な表現が考えられます。このように、理系英語に頻出する表現を、覚えるというより、文章を読み込むことによって慣れて行くことが大切です。
|